
訪問介護と訪問入浴の違いとは?費用・手順・注意点まで初心者向けに徹底解説!
「訪問介護と訪問入浴ってどう違うの?」「うちにはどちらが合うのかな…」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
どちらも在宅での入浴支援を目的としたサービスですが、内容や対象者、費用、準備などに明確な違いがあります。
本記事では、訪問介護の入浴介助と訪問入浴の違いをわかりやすく整理し、利用までの流れや費用感、注意点、ご家族ができるサポートを解説します。
✅この記事でわかること
- 訪問介護と訪問入浴の具体的な違い
- 利用条件・対象者・医療対応の範囲
- サービス開始までの流れと当日の準備
- 費用相場と利用頻度の目安
- 利用時のメリット・デメリットと家族の関わり方
ぜひ最後までご覧いただき、ご自宅にぴったりの入浴支援を見つける参考にしてください。
訪問介護と訪問入浴の違いとは
「訪問介護の入浴介助と訪問入浴って、どう違うの?」と迷われる方も少なくありません。
どちらも在宅での入浴支援を目的としていますが、対応できる内容や利用条件には明確な違いがあります。
ここでは、それぞれのサービスの特長や違いをわかりやすく整理し、選び方のヒントもあわせてご紹介します。
訪問介護の「入浴介助」とは

訪問介護の入浴介助は、自宅の浴室で安全に入浴できるよう、ヘルパーが身体介助を行うサービスです。
たとえば、浴槽への出入りの補助や、体を洗う際の支え、着脱衣の介助などが含まれます。
ただし、利用者本人が浴室まで歩いて移動できることが前提となるため、身体機能がある程度保たれている必要があります。
訪問入浴とは
訪問入浴は、専用の浴槽を積んだ入浴車が自宅へ訪問し、看護師を含む3人1組のスタッフが入浴支援を行うサービスです。
自宅の浴室が使えない場合や、ベッド上で生活している方でも、清潔とリラクゼーションを保つことができます。
また、看護師によるバイタルチェックや、医療的な配慮のもとでの入浴が可能な点が、訪問介護との大きな違いとなります。
どちらを選ぶべき?
選択のポイントは、利用者の身体状況と、どこまでの支援が必要かという点です。
たとえば、自力で浴室へ行ける方には訪問介護の入浴介助が適していますが、寝たきりや医療的ケアが必要な方には、看護師が同行する訪問入浴が安全といえるでしょう。
「なんとなく不安…」と感じたら、まずはケアマネジャーに相談することをおすすめします。
利用者本人の状態に最適なサービスを一緒に検討してもらえるはずです。
訪問介護の入浴介助の対応範囲

「訪問介護の入浴介助って、どこまでやってもらえるの?」という疑問は多くのご家族が抱えるポイントです。
たしかに、在宅での入浴支援といっても、介護保険の範囲内でできること・できないことがあるのが実情です。
ここでは、訪問介護における入浴介助の内容と、その限界について整理し、誤解を防ぐための基礎知識をご紹介します。
介護保健で対応される範囲
介護保険での入浴介助は、身体介護として認定された時間内に、浴室内で安全に入浴できるよう支援するサービスです。
ただし、あくまで生活支援ではなく、利用者の自立を助ける範囲に限られるため、医療的ケアは含まれません。
| 対応できること | 対応できないこと |
| 浴槽への出入りの介助 | 点滴やカテーテル管理などの医療行為 |
| 洗身・洗髪の補助 | 傷口処置や体調チェックなど看護師の対応が必要なもの |
| 入浴前後の着脱衣・整容の介助 | バイタル測定・体調判断など医療判断が伴う内容 |
このように、訪問介護の入浴介助は「できること」と「できないこと」を明確に区別して理解することが重要です。
利用対象者と条件
訪問介護の入浴介助を利用するには、要介護認定を受けていることが前提となります。
また、自宅の浴室まで自力または軽介助で移動できることも条件のひとつです。
たとえば、ベッド上での生活が中心になっている方や、浴室への移動が困難な方は、訪問介護ではなく訪問入浴の対象となるケースが多いです。
身体状況や住環境により判断が異なるため、事前にケアマネジャーと十分に相談しておきましょう。
医療行為との違い
訪問介護のヘルパーは、原則として医療行為を行うことができません。
たとえば、以下のようなケアは、訪問介護では対応外となります。
|
こうした対応が必要な場合は、看護師が同行する訪問入浴や、訪問看護との併用が適しています。
「万が一のときが不安…」というご家族には、訪問入浴の利用が安心につながるでしょう。
訪問介護・訪問入浴サービスの流れと準備

「サービス当日って、どんな感じ?」「何を用意すればいいの?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
実際、訪問介護や訪問入浴は在宅で行うサービスだからこそ、事前の準備や当日の段取りがとても重要です。
ここでは、利用開始までの流れと、当日必要になる物や注意点をわかりやすく解説します。
利用開始までの手続き
訪問介護や訪問入浴を利用するには、まずケアマネジャーへの相談が第一歩です。
サービスの必要性や回数、体調面の確認を行いながら、介護プランの中で必要性を判断していきます。
手続きの流れは以下の通りです。
|
事前の話し合いがしっかりできていれば、当日もスムーズに進みます。
サービス当日の流れ
訪問介護・訪問入浴のサービス当日は、安全かつ効率よく入浴できるようにスタッフが丁寧に対応してくれます。
以下は、一般的な訪問入浴サービスの一例です。
|
訪問介護の入浴介助も同様に、利用者の体調に応じて臨機応変に対応してもらえます。
安心して任せられるよう、事前の説明と準備が鍵になります。
事前に準備しておくべきもの
訪問入浴・訪問介護どちらの場合も、あらかじめ必要な備品をそろえておくことで当日の対応がスムーズになります。
以下は基本的な準備物の一例です。
|
特に冬場や寒い日には、事前に部屋を暖めておくだけでも利用者の負担が軽減されます。
「これでいいのかな…」と迷ったときは、事業所に確認するのが確実です。
訪問介護と訪問入浴の料金・頻度の比較
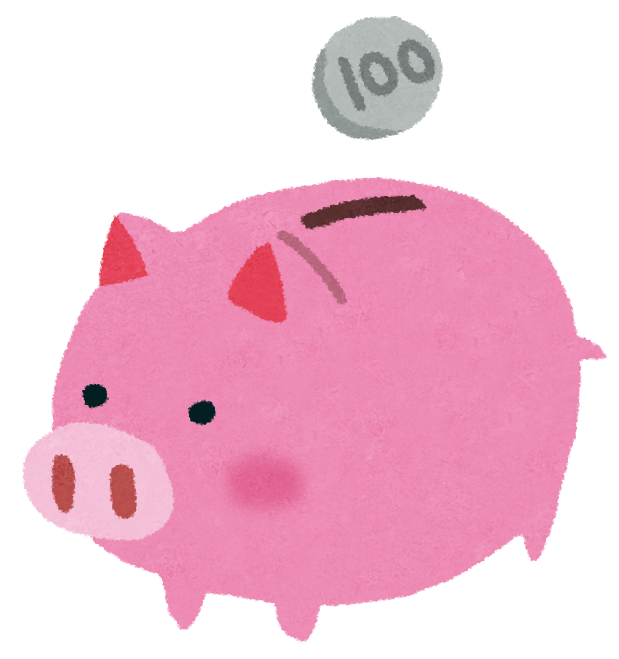
「費用はどれくらい?」「週に何回くらいが適切?」と悩む方は少なくありません。
訪問介護・訪問入浴はどちらも介護保険の対象ですが、内容や体制の違いにより料金も異なります。
ここでは、それぞれのサービスにかかる費用感と、利用頻度をどう決めるべきかをわかりやすく整理します。
訪問入浴の料金目安
訪問入浴介護の費用は、介護保険が適用されるため、自己負担は1~3割で済みます(※以下は1割負担の目安です)。
| サービス内容 | 単位数(全国平均) | 事故負担の目安(1割) | 備考 |
| 訪問入浴(1回) | 1,250単位 | 約1,265円 | 看護師+介護職員による3人対応 |
| 清拭・洗髪加算など(任意) | +50~100単位前後 | 約50〜100円程度 | 洗髪・褥瘡処置などが加わる場合 |
| 特別地域加算など(任意) | 地域で異なる | +数十〜百円程度 | 地域差あり(東京都など都市部で高め) |
たとえば、要介護3の方が週1回利用する場合、月額5,000〜6,000円程度が目安となります。
正確な金額は、地域や事業所の加算設定により異なるため、事前の確認が安心です。
訪問介護の入浴介助の費用
訪問介護での入浴介助は、「身体介護」に分類され、所要時間に応じて報酬が定められています(以下は1割負担の目安です)。
| 提供時間 | 単位数 | 自己負担の目安(1割) | 主な支援内容 |
| 20分以上30分未満 | 287単位 | 約291円 | 更衣・移動・浴槽への移乗などの介助 |
| 30分以上60分未満 | 405単位 | 約410円 | 洗身・洗髪・安全確認・見守りも含まれる |
| 60分以上90分未満(例外) | 584単位 | 約592円 | 対応範囲が広がるが要件あり(頻度は少ない) |
1回あたりの金額は小さいですが、週3回以上など高頻度で利用する場合は合計金額が大きくなることもあるため、支給限度額に注意が必要です。
利用頻度の決め方
入浴サービスの頻度は、医師の指示や利用者本人の体調・生活状況に応じて調整されます。
たとえば、皮膚疾患がある方は週2〜3回が推奨されることもありますが、体力的な負担を考えて週1回から始めるケースも少なくありません。
また、訪問介護と訪問入浴を併用し、日によって使い分ける方法もあります。
ケアマネジャーと相談しながら、本人の希望やご家族の介護力に応じたプランを立てましょう。
訪問介護入浴のメリットとは?家族と本人にうれしい効果
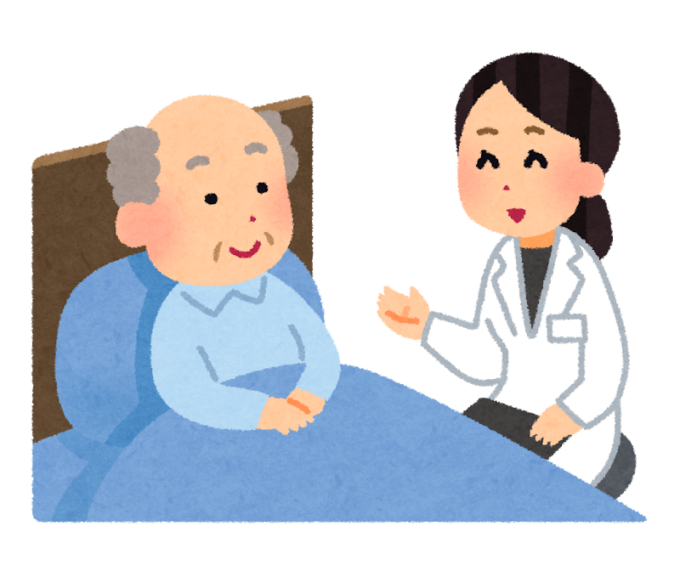
訪問介護入浴や訪問入浴サービスには、単なる入浴支援以上の価値があります。
安心・快適に入浴できる環境を整えることで、利用者の生活の質(QOL)や、ご家族の精神的負担にも良い影響をもたらします。
ここでは、特に実感されやすい3つのメリットをご紹介します。
①自宅で安全に入浴できる安心感
訪問介護入浴の大きな魅力は、慣れた自宅で安心して入浴できることです。
浴槽への出入りや洗身など、滑りやすい場面でもヘルパーがしっかり介助してくれるため、転倒のリスクがぐっと下がります。
たとえば、以前は浴室で転びかけた経験がある方でも、安心して入浴を続けられるようになったという声も多いです。
②医療職の同行による健康管理
訪問入浴では、看護師が同行して体調の確認や健康チェックを行ってくれるのが特徴です。
血圧や体温の測定を通じて、入浴に問題がないかを判断してくれるため、持病のある方でも安心してサービスを受けられます。
入浴中に体調が急変した際も、看護師がその場で対応できるというのは大きな安心材料です。
②家族の負担が軽減される
在宅での入浴介助は、家族にとっても大きな体力・精神的負担になることがあります。
特に重度の要介護者を支えるご家族にとっては、衣類の着脱や浴室内での支えなど、1つひとつが重労働です。
訪問入浴を導入することで、介護の負担が分担され、ご家族にもゆとりが生まれるのは大きなメリットといえるでしょう。
訪問介護入浴のデメリットと注意点とは?導入前に確認したい3つのこと
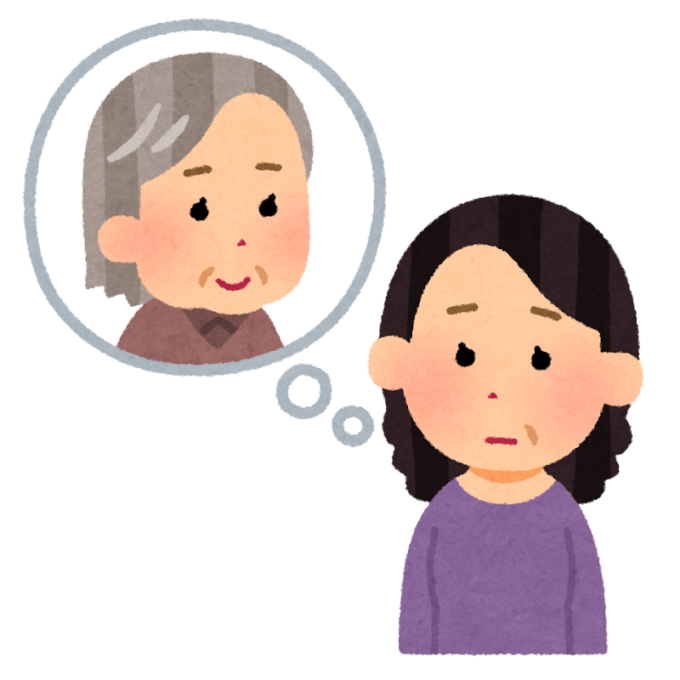
訪問介護入浴は便利な反面、すべての家庭にとって「万能なサービス」とは限りません。
特に導入前には、費用やスペース、予約の取りづらさといった点で注意が必要です。
ここでは、実際に利用する前に押さえておきたい3つのポイントを具体的に解説します。
①費用がかさむケースもある
介護保険が使えるとはいえ、サービスの回数や加算項目が増えると自己負担が高額になることがあります。
たとえば、訪問入浴を週2回ペースで利用すると、月額1万円以上の自己負担になることも珍しくありません。
さらに、居宅療養管理指導や処置の加算が付く場合には、想定以上の費用がかかるケースもあります。
②設備設置にスペースが必要
訪問入浴では、専用の浴槽や機材を室内に設置する必要があるため、スペースの確保が求められます。
バリアフリーでない住宅や、室内の通路が狭いお宅では、設置に苦労する場合があります。
たとえば、ポータブル浴槽が玄関を通らない、機材の搬入が2階に難しいといった問題が起こることもあります。
③サービス提供時間に制約がある
訪問入浴は、看護師と介護スタッフが3人1組で訪問するため、対応できる枠に限りがあります。
特に利用者が多い地域や曜日(たとえば月曜・金曜の午前中)は予約が集中しやすく、希望通りの時間が取れないことも・・・。
また、急な変更がしづらいため、柔軟なスケジュール調整が難しい点も留意しておく必要があります。
訪問介護入浴を上手に活用するために家族ができること

訪問介護入浴をより快適に、そして長く活用していくには、家族のちょっとした工夫や関わりが大きな力になります。
サービスを受けるだけでなく、連携や環境づくりを意識することで、本人の満足度もぐんと高まるでしょう。
ここでは、ご家族ができる3つのサポートポイントをご紹介します。
ケアマネとの連携が重要
訪問介護入浴を効果的に活用するには、ケアマネジャーとの綿密な連携が欠かせません。
たとえば、「最近皮膚の乾燥が気になる」「入浴後ぐったりしてしまう」など、小さな変化も早めに伝えることで、入浴の頻度や内容、必要な加算対応などを調整しやすくなります。
遠慮せず相談する姿勢が、良質なサービスにつながります。
複数サービスの併用でQOLを向上
訪問入浴だけに頼らず、デイサービスや福祉用具のレンタルと併用することで、生活全体の質が向上します。
たとえば、入浴は訪問で対応し、外出やリハビリはデイサービスで補うという使い分けも効果的です。
入浴のたびにお風呂用の椅子やリフトを使えば、介助も軽くなり、負担感が軽減されることもあります。
自宅環境の整備と確認ポイント
安全に入浴サービスを受けるには、自宅の設備や動線をあらかじめ整えておくことも大切です。
たとえば、浴室までの通路を片付けておいたり、室温を適温に保ったりといった配慮が、快適さを支えます。
また、ポータブル浴槽や給湯器の電源位置など、事前にスタッフが確認しやすい環境づくりもご家族ができるサポートのひとつです。
訪問介護・訪問入浴のまとめ
訪問介護の入浴介助と訪問入浴には、それぞれ異なる特徴と役割があります。
身体状況や生活環境に応じて使い分けることで、入浴の安心感と快適さが大きく高まります。
ケアマネや専門職と連携しながら、ご本人とご家族に合った方法を無理なく選んでいきましょう。












