
介護ストレスの発散方法!介護疲れとうつを和らげて健康を取り戻そう
「愛する家族なのに、なぜイライラしてしまうのだろう」
「本当の私はもっと優しいはずなのに…」
介護を自分一人で抱え、さらに責任感が強いほどストレスは溜まりやすくなります。
孤軍奮闘している介護は心身の負担も大きく、場合によっては介護うつを招きやすくなるため、ストレスを発散する必要があるのです。
本記事を読むことで
- 介護ストレスの5つの原因
- 介護ストレスを放置する2つの危険性
- 介護ストレスを回避するための心構え
- 介護ストレスの発散方法
- 介護ストレスを防ぐために人の力を借りる
といった介護ストレスを回避する方法がわかります。
最後までぜひご覧になり、介護疲れとうつを和らげて健康を取り戻してください。
介護ストレスの5つの原因

日々、絶え間なく続く介護生活により、心身の負担や精神的な不調が重なってストレスを感じる場合があります。
介護ストレスとは、自身の心身が悲鳴をあげている状態を指すほか、経済面や時間的な負担など複雑な要素の絡み合いによって生じるのです。
厚生労働省の「ストレスの原因の割合調査」によると、男女ともに「家族の病気や介護」のストレスが高い割合になっています。
出典:厚生労働省「介護の状況(性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの原因の割合)」
こうした介護に関わるストレスの一因として、主に次の5点が挙げられます。
| ①身体的ストレス ②精神的なストレス ③経済的な負担 ④時間の制約 ⑤認知症介護によるストレス |
ここでは、介護ストレスの原因を詳しくみてみましょう。
①身体的ストレス
自宅での介護は、要介護者の身体的なサポートを行う場面が多く、身体的な負担は免れません。
介護者の起床や移動、あるいは入浴やおむつ交換などは身体を持ち上げたり動かすことが多いため、腰や背中に疲労がたまりやすいものです。
また、夜間のおむつ交換では、介助者の睡眠時間も短くなるため、健康を損ねる危険性もあります。
特に、介護者が高齢の場合、身体的な負担は大きく、介護者自身も病気になる恐れもあるのです。
②精神的なストレス
自分の時間が減少する介護生活では、要介護者の健康状態の変化や予期せぬ問題の対応などにより精神的なストレスを生じさせます。
また、要介護者とのコミュニケーションや介護スタッフとの関係性の維持もストレスの原因になるでしょう。
もっとも、慣れない介護を自分一人で行っている人や、介護による相談相手がいない場合等も精神的なストレスの原因です
③経済的ストレス
介護の負担は家庭の経済状況も大きく圧迫するものです。
特に、普段の生活費に加えて「介護サービス費用」や「医療費」といった高額費用の出費も多く、紙おむつやデイサービスでの食事代金などは自己負担となります。
場合によっては介護のため会社を退職したり、時間短縮するなどして収入が減少する人もいるでしょう。
結果的に、経済的に日常生活の維持が厳しくなり、介護そのものがストレスになる状況に陥ってしまいます。
④時間の制約
自宅での介護が始まると、介護者自身の時間が持てなくなり、趣味やリラックスといった心の休息時間も削られます。
また、介護に重点を置く生活によって、従来からの予定を変更する必要があったり、日常における活動を中断しなければならない場面も増えていきます。
こうした時間の制約や、介護者の心身ストレスを増長させ、介護うつ等を引き起こす可能性もあるのです。
⑤認知症介護によるストレス
大切な人が認知症を患い、人格や行動が変わっていく様子を見ることは、介護者にとって大変な苦痛でありストレスの要因になるものです。
また、認知症によって予測不可能な行動を起こすことも多く、これもストレスを増加させています。
特に一人で介護している場合、孤独感や無力感におそわれ、介護うつにつながる危険性も隠れているのです。
| こうした介護ストレスが高まると、要介護者への暴言や暴力といった虐待に至る場合もあるため。適切なサポートと休息が不可欠です。 |
介護ストレスを放置する2つの危険性

介護によるストレスを放置すると、次の危険性を招く恐れがあります。
| ①要介護者への虐待 ②「介護うつ」の発症 |
ここでは、介護ストレスを放置した場合にはらむ危険性を具体的にみてみましょう。
要介護者への虐待
心身的な負担の大きい介護は、日々の疲れが蓄積されやすく、同時にストレスも増大していきます。
特に長期間にわたって介護をしていると、場合によっては虐待につながる恐れもあります。
平成17年度の東京都の調査によると、虐待を受けた高齢者のおよそ7割の人に認知症の症状が見受けられました。
出典:東京都福祉局「認知症と高齢者虐待(東京都高齢者虐待事例情報調査の結果について)」
もっとも、身体的虐待のほかにも、無視や暴言あるいは嫌がらせといった心理的虐待、要介護者の世話をしない行為や、資産を勝手に使い込む経済的虐待も含まれています。
「介護うつ」の発症
介護が始まると、介護に割かれる時間が増えていき、介護者は常に心身の緊張や不安を抱えながら過ごすことになります。
自身がリフレッシュできる時間や睡眠時間も極端に削られ、こうしたストレスが積み重なって「介護うつ」に陥る人も少なくありません。
「介護うつ」の主な症状は通常の「うつ病」と同じく、食欲不振や不眠・イライラ・口数の減少・突然悲しくなり涙ぐむといった変調をきたすようになります。
状態によっては「死にたい・・・」「消えたい・・・」などの自殺念慮を持ち、自死への危険も高まる症状に襲われるのです。
介護ストレスを回避するための心構え
日々の介護においてストレスを最小限に抑えることは、心身バランスを保つ上で大変に重要です。
そこで、介護ストレスを回避するための心構えとして次の3つが挙げられます。
|
たった3つの心構えですが、穏やかな精神状況を維持するためにも大切な事項です。
ぜひ心に留めて、実践してみてください。
頑張りすぎない
介護者のなかには必要以上に頑張りすぎてしまい、心の余裕を見失ってしまう人もいるでしょう。
何もかも完璧な介護を行う必要はなく、肩の力を抜いて気持ちにゆとりを持つことが重要です。
長い介護生活を無理なく続けるためにも、ご自身の心身バランスを保ち、自分の時間を大切にすることを心掛けましょう。
一人で抱え込まない
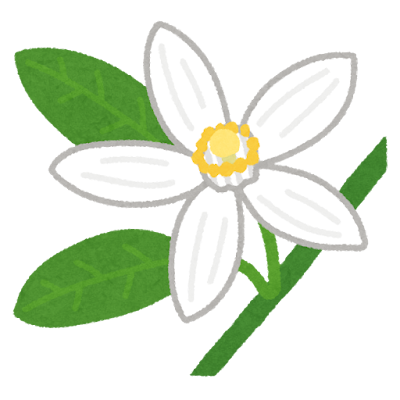
介護は決して一人で抱え込まず、身内はもちろん周囲の人や介護サービスを頼ってみてください。
一人で介護を行うと次第に「なぜ自分だけが・・・」「どうして手伝ってくれないの・・・?」と不満がたまり、介護うつや虐待といった危険性も高まります。
こうした最悪な事態にならないよう、親戚や周囲の者と連携し、介護の役割分担の話し合いをおすすめします。
遠方に住んでいていて、直接介護に関われない人には経済的な援助をお願いするなど、介護にかかる心身的な負担を少しでも軽減できるように対処しましょう。
他の要介護者と比べない
認知症の症状や要介護者の状態は個々によって異なり、それぞれの心身状態・生活環境・支援の必要度も違ってきます。
さらに、介護者自身が直面する問題も異なるため、他の要介護者と比較しても意味がありません。
「隣の芝は青く見える」の諺通り「同じ介護度なのに、なぜ私の親は重い状態なのだろう」と、ついマイナス思考に陥りやすいものです。
| 他の人の症状を見比べる必要はありません。
ご自身のペースに合わせて、自分らしい介護を行うことが介護ストレスの軽減に繋がります。 ご自身の介護への取り組みをきちんと認めてあげて、自身を最大限の褒めたたえてあげてください。 |
介護ストレスの発散方法
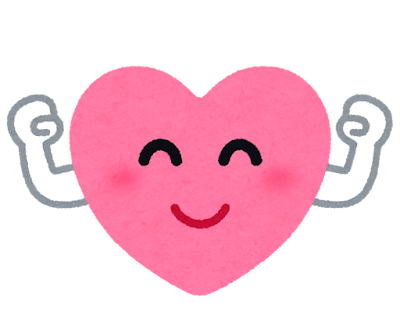
介護ストレスの発散は、介護者の心身の健康を維持することはもちろん、意思を伝えにくい要介護者を真摯に守ることに繋がります。
ここでは下記のように、介護ストレスの主な発散方法をご紹介します。
|
介護ストレスを軽減するには、日頃からリフレッシュできる時間を作り、睡眠時間を確保して疲れを溜めないことが大切です。
①家族や友人に愚痴を聞いてもらう
心を許せる相手には、心の奥底に溜めてた辛さも本音で伝えることができるでしょう。
誰かに胸の思いを伝えることは心も軽くなり、介護ストレスを発散するのに役たちます。
愚痴を聞いてくれる相手がいない場合は、ケアマネージャーやかかりつけ医に聞いてもらいましょう。
②日光を浴びる
日光を浴びることで幸せホルモンが分泌されて精神が落ち着き、集中力を高める働きがあります。
これは「セロトニン」という神経伝達物質が脳内に行き渡るためです。
また、カルシウムを吸収させたり骨の健康を促すなど、心身バランスを整えるために重要な役目をしています。
| 介護の息抜きに、一日15~30分程度日光を浴びて、心身の健康維持に努めましょう。 |
③十分な休息と睡眠をとる
十分な教則と睡眠は、心身疲労を取りのぞくために不可欠です。
特に睡眠不足は自律神経やホルモンのバランスが崩れ、心身状態に悪影響を及ぼします。
介護ストレスによって入眠が難しい場合は、毎日同じ時間に布団に入り、日中は日光を浴びたり軽い散歩をすることをおすすめします。
④おいしいものを食べる

どんなに疲れていても、おいしいものを食べると幸せな気持ちになるでしょう。
この「幸せな気持ち」に導くものは、タンパク質に含まれるトリプトファンのおかげです。
トリプトファンを多く含む主な食材は次の通りです。
|
上記を参考に、食べやすくて消化の良い食材を積極的に摂取して、介護ストレスを軽減させましょう。
⑤一旦その場から離れる
四六時中、在宅介護に携わると、要介護者にはもちろん、家族やヘルパーの方に対してストレスが爆発してしまうかもしれません。
そうした事態を招かないように、まずは一旦その場から離れ、深呼吸をして心を落ち着かせたり、下記でご紹介する「ツボ押し」でイライラを鎮めてみてください。
手の親指と人差し指の間(合谷=ごうこく)を押してリラック効果が期待できます。
※気持ちいい程度の強さで押し、押しすぎにはくれぐれも注意してください。 |
⑥何も考えずにぼーっとする
「ぼーっ」とする時間は無意味なように感じますが、実は脳にとっても貴重なリフレッシュタイムに繋がるのです。
「ぼーっ」とした状態は、脳内で「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」が活発化され、創造性が高まるとともに脳が休まり幸福感をもたらすことを脳科学的にも解明されています。
何も考えずに「ぼーっ」とするひとときで、疲れた心を落ち着かせてみると良いでしょう。
⑦大声で歌をうたってみる

お腹の中から大きな声で歌をうたうことは、ストレス発散効果として絶大です。
自律神経が張り巡らされた横隔膜は大声を出すことで刺激され、副交感神経が優位になります。
副交感神経は「リラックス状態」にある場合に出現するため、大声で叫んだり歌うことで介護ストレスの解消につながるのです。
| 介護で疲れた時や辛い時、楽しい時も大きな声で歌うことは、ストレス発散効果のほか、唾液量が増えてアンチエイジング効果も期待できます。 ただし、大きな声で叫んだり歌をうたう場合は、車の中や一人カラオケなど、近所の迷惑のかからない場所で行ってください。思う存分声を出し、溜まりすぎたストレスを声と一緒に追い払いましょう。 |
⑧好きな音楽を聴く
好きな音楽を聴くことで、幸福感をもたらす神経伝達物質(セロトニンやドーパミン)が分泌されて、不安やストレスを出すホルモンを抑制すると同時に、心神状態をリラックスさせる効果があります。
また、好きな音楽によって自律神経が正常化し、呼吸や心拍数が安定して心身的なストレスが軽減されるのです。
介護の合間の音楽は気持ちも癒やされるので、要介護者に対しても心穏やかに対応できる「お守り効果」といえるでしょう。
⑨イライラした思いを紙に書き出す
日々の介護でストレスを感じたら、そのイライラを「紙」に書き出してみましょう。
文章に限らず意味不明なイラストや「落書き」でもかまいません。
紙に書き出すことで次の2つの効果があるのです。
|
他者に見せる必要もないので、ありのままの気持ちを自由に書いて、心のメンテナンスを図りましょう。
⑩心のなかで6秒間カウントする
日々の介護でイライラする気持ちが強くなったら「6秒間」のみ怒りを堪えて我慢することで、イライラの感情が消えていきます。
これは「6秒間ルール」と呼ばれ、アンガーマネジメントと呼ばれる心理トレーニングの一つです。
アンガーマネジメントを身につけることで自身の感情に左右されず、自分や相手さらに周囲の状況を冷静に判断できるようになり、介護ストレスにも大変役立ちます。
⑪適度な運動をする

適度な運動を行うことで、介護ストレスのネガティブ気分もスッキリし、心身をリラックスさせるほか良い睡眠への導いてくれます。
特に、体内に良い空気を取り入れる「有酸素運動」は血液の循環を良くし、脳内の疲れも洗い流す作用があります。
介護の合間の1日20分程度の散歩を目安に継続することで、その大きな効果を実感できるでしょう。
⑫ゆっくり湯船につかる
ストレス解消にはぬるめ(38度~40度)の湯船に10~15分程度つかると良いとされています。
リラックスするには副交感神経を刺激させる必要があり、ぬるめの湯船にゆったりつかることで副交感神経が活発になってリラックス効果が高まるのです。
さらに、睡眠効果や血行促進、疲労回復、肩こりや腰痛の緩和などその効果は計り知れません。
湯船にお気に入りの入浴剤やアロマオイルを数滴垂らしたり、好きな音楽をかけるなどご自身に最適なバスタイムを楽しみましょう。
⑬部屋を掃除して花を飾る
部屋のなかに綿埃が充満していたり、キッチンには汚れた食器が無造作に置かれていると、それだけでストレスを抱える原因になります。
休みの日に部屋を掃除して、お気に入りの花を飾るだけで心身が癒やされるものです。
これを「フラワーセラピー」といいますが、花を生けることで次の効果が期待できます。
|
忙しい介護生活ですが、掃除後の部屋に花を飾って気分転換を図るのもおすすめです。
⑭お気に入りの香りを嗅ぐ

アロマテラピーとは、植物から取れる精油(エッセンシャルオイル)を利用して、心身の疲れを癒やす「芳香療法」です。
「香薬」と呼ばれる芳香植物には、香りの力によって次の役割を期待できます。
|
エッセンシャルオイルの種類は200以上と豊富に揃い、それぞれ香りや特徴も異なります。
以下を参考に、ストレスの違いによってご自身にあったエッセンシャルオイルを使ってみてください。
| ストレスの種類 | エッセンシャルオイル | 香り |
| 落ち込みやすい | レモンバーム | 柑橘系特有の爽やかでフルーティーな香り |
| 不眠・気分の落ち込み | カモミール | 甘く爽やかな香り |
| 不眠・イライラ | ラベンダー | フルーティーで優しい香り |
| 疲れが取れないとき | ローズ | 高級感あふれる深い花の香 |
| 集中力が続かないとき | ペパーミント
ローズマリー |
メントールの透き通った香り 野生美溢れたクリアな香り |
これはNG!介護ストレス発散法
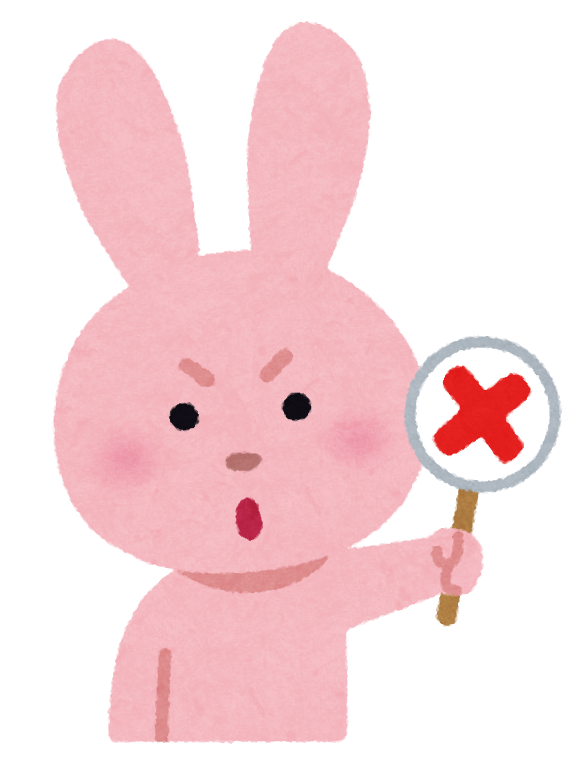
介護ストレスの発散方法を一歩間違えると健康を損ない危険です。
例えば、次のような間違った発散方法なので注意してください。
|
ここでは、NGな介護ストレス発散方法をみてみましょう。
過度な飲酒
適度な飲酒はリラックス効果があって介護ストレスも解消しますが、飲みすぎるとかえって逆効果になります。
例えば、睡眠薬代わりとして飲酒を続けると、睡眠の質が悪くなり夜中に目が覚めやすく、飲酒量も増えて依存症の恐れもでてきます。
また、長期間にわたる飲酒によって肝臓障害や糖尿病、脂質異常症、高血圧といった生活習慣病を招きやすく、様々な病気の原因になるため注意が必要です。
やけ食い
やけ食いは、介護ストレスから逃れるための簡単な手段かもしれません。
ですが、カロリーを摂取し過ぎて体重が増えてしまい、太ることへのストレスから食べたら吐く、あるいは下剤や利尿剤の使用に走ってしまう人もいます。
やけ食いが新たなストレスを生まないように、本記事でご紹介したようなストレス発散方法を試してみてください。
睡眠薬の常用
介護ストレスでなかなか眠れず、睡眠薬に頼る人も多いことでしょう。
しかし、睡眠薬には依存性があり、常用によって身体に悪影響を及ぼします。
例えば、イライラ、不安、不眠、焦燥、頭痛、抑うつ、吐き気などの症状です。
睡眠薬は心身へのリスクも踏まえ、医師の指導のもと上手に利用しましょう。
参考元:千葉県ホームページ「睡眠薬を飲んでいるとクセになると聞いたのですが」
介護ストレスを防ぐために人の力を借りよう!

毎日の介護生活の中で、ストレスを我慢し続けると心身への悪影響は免れません。
そこで、介護ストレスを軽減するためには次のように、人の手を借りることも視野に入れましょう。
|
介護ストレスは誰でも感じるものですが、最適な対処法で乗り越えることは可能なのです。
専門家に相談する
介護の辛い悩みは、ケアマネージャーや地域包括支援センター、あるいは主治医に相談しましょう。
特にケアマネジャーは介護のプロフェッショナルで専門知識を持ち、要介護者に合わせたケアプランを作成してくれます。
相談にしくい問題でも気軽に話せるので、介護中の孤立感も解消することでしょう。
介護に関する知識を身につける
介護者自身が介護に関わる知識を身に着けることで、移乗交換やおむつ交換、排泄介助などが正しく行えます。
また、正しい介護知識によって、介助に伴う腰の痛みも予防できるなど、安全な介護生活を送ることができるのです。
なお、自治体によってはファミリー向けの介護教室を実施している場合もあるので、積極的に参加してみましょう。
デイサービスやショートステイを活用する
デイサービスやショートステイの利用は、要介護者はもちろん介護者にとっても大きなメリットがあります。
介護者は自身の時間を確保でき、介護生活で遠のいた趣味や買い物などができるので、大きなリフレッシュタイムになれます。
要介護者は、デイサービス等を通じて機能訓練やレクリエーションがあり、専門家達による心身のサポートも充実しています。
いずれも、ケアマネジャーや地域包括支援センターにまずは相談してみてください。
施設への入所を検討する
一人で抱える介護生活は、ストレスの大きさも想像をはるかに超えたものでしょう。
在宅介護に限界を感じている人や親族等からの協力が厳しい場合、施設への入居を検討してみましょう。
介護施設に入居することで介護者の心身ストレスは軽減され、要介護者も専門家に委ねることで介護状態が落ち着く場合もあるのです。
施設への入居は要介護度によって選択する必要がありますが、万が一に備えてケアマネジャーに相談なさることをおすすめします。
介護ストレスの発散方法のまとめ
介護によって、長年の生活スタイルが一気に変わるため、どんな人でも大きなストレスを抱えるようになります。
しかし、知らず知らずのうちに介護者の心身状態は悪化していき、取り返しのつかない事態になりかねません。
そのため、小さなストレスを決して見逃さずに専門家に相談したり、本記事でご紹介したストレス発散法を活用し、ストレスに負けない心身を目指しましょう。












