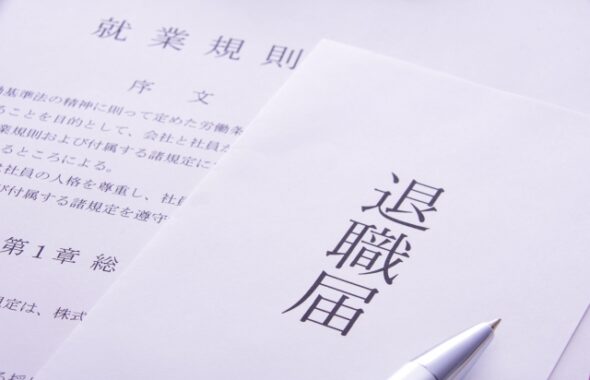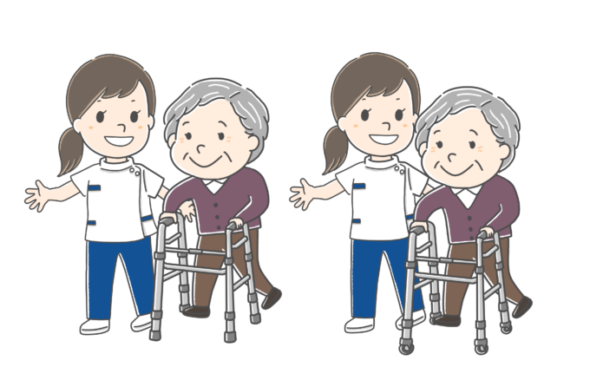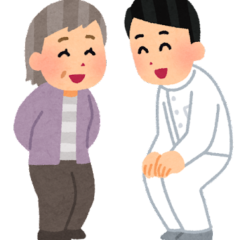要支援認定の仕組み・サービスをご紹介!適切な利用で介護予防に努めよう
介護保険について調べると、「要介護・要支援」という言葉が出てきます。しかしいざ介護保険を利用する場面で「違いが分からない」という方も多いでしょう。
認定の申請する前に要介護・要支援の特徴や違いを知っておくと、今後家族がどの程度介護に関わればよいかが明らかになります。本記事では、要支援の基準や利用できるサービス、サービス利用までの流れをご紹介します。
要支援認定とは
要介護認定では、大きく「自立・要支援・要介護」に分類されます。要支援認定とは、この分類の一つです。それぞれのどのような身体状況や基準で分類されるのかを確認しましょう。
日常生活でどれくらい「支援」が必要かの指標
要支援認定とは、日常生活でどれくらい「支援」が必要かの指標です。要介護状態よりは軽く「1人で生活可能だが、部分的に介護を必要な状態」を指します。
要介護認定では身体機能や認知機能などをもとに、「自立」「要介護」「要支援」に分けられ、それぞれ受けられるサービスや介護保険の支給限度額が異なります。
1人で日常生活を送ることができる「自立」
自立とは、基本的に1人で日常生活を送ることができる状態で、歩行や起き上がりなどの基本的動作はもちろん、薬の管理や電話の利用など自分のことを自分でできる状態です。
介護サービスの支援が必要ないとみなされ、介護保険を利用してサービスを受けることはできません。
日常生活で一部支援が必要になる「要支援」
要支援とは、日常生活で一部支援が必要になる状態を指します。日常生活に必要な基本動作は問題ありませんが、掃除や薬の管理など比較的複雑な動作では支援が必要な状態です。要支援は2段階のレベルがあり、数が大きくなるほど支援の必要性が生じます。
要介護状態の一歩手前とされ、状況が悪化しないよう「介護予防サービス」を受けることができます。
日常生活が困難で介護が必要な「要介護」
要介護とは、日常生活に必要な基本動作を1人で行えない状態を指します。入浴や排せつなどの動作も困難で、他者の介助・介護を必要とします。
要介護には5段階のレベルがあり、要支援同様数値が大きくなるほど介護の必要が生じます。認定された介護度によって、サービスを受けられる時間や介護保険の支給限度額が異なるため注意が必要です。
要支援の認定基準
要支援・要介護認定は、まずコンピュータで1次判定が行われます。その際に用いられるのが「要介護認定基準時間」です。要介護認定基準時間は二次判定にも反映され、認定調査、医師の意見書などから総合的に、「自立・要支援・要介護」の認定がされます。
介護に必要な「要介護認定等基準時間」が用いられる
「要介護認定基準時間」とは、「介護の手間」を数値化して要介護度を判定する指標です。要介護認定基準時間は厚生労働省が定めた基準で、「介護に費やす時間」と「認知症の有無」を加味して時間で表します。
要介護認定基準時間は直接介護サービスを受けられる時間ではなく、あくまでも介護の必要性を量る指標です。数値だけで判断されるわけではなく、さまざまな角度から保健・医療・福祉の専門家が二次判定(介護認定審査会)で話し合い決定されます。
「要介護認定等基準時間」にカウントされる行為
要介護認定基準時間としてカウントされるのは、以下の行為です。
| 行為 | 具体的な内容 |
| 直接生活介助 | 食事/入浴/排泄などの介助 |
| 間接生活介助 | 洗濯/掃除などの家事援助 |
| 問題行動関連行為 | 徘徊時の探索や排泄失敗時の後始末 |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練/日常生活訓練など |
| 医療関連行為 | 褥瘡の処置や診療補助、輸液の管理など |
さらに、「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」などから「認知症加算」に該当するかを判定し、これらの状況と合わせてコンピュータで1次判定をします。要介護認定基準時間が分かると、どの行為に介護時間を要しているかが明らかになります。
「要介護認定等基準時間」による要支援・要介護分類
要介護認定基準時間は、区分ごとに以下のように分類されます。
| 要介護度 | 要介護認定基準時間 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護1 | |
| 要介護2 | 50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護5 | 110分以上またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2と要介護1については、要介護認定基準時間が同じ事が分かります。具体的にどのような基準で「要支援・要介護」が判定されるのかを以下で確認しましょう。
要支援と要介護の分かれ目
要支援と要介護は、上の表からも分かる通り、非常に近い状況にあります。要介護認定基準時間は同じため、以下の2つのポイントから判定されます。
ポイント1:状態の安定性
ポイント1つ目は「状態の安定性」です。「状態」とは病状を表すのではなく、全体的な身体状況を指し、「介護が必要となる変化が起こるか」ということです。
介護が必要となる可能性が考えられ、「認定後6カ月以内に再評価が必要」と判断されれば、「要介護1」と判定されます。
ポイント2:認知症の度合い
認知症の度合いも、要支援/要介護の判定基準になります。認知症の度合いは、「認知症高齢者の日常生活自立度」で7段階にわたって評価され、度合いが重いと「要介護」と判定されることがあります。
最終的には介護認定審査会で決定されるため、参考程度に覚えておくと良いでしょう。
表で納得!要支援認定を受けて利用できるサービス
「要支援」の認定を受けた方は、「介護予防サービス」を利用することができます。以下のサービスから自分に合ったサービスを利用しましょう。
| 訪問サービス | 訪問入浴:自宅で入浴介助を提供する。 |
| 訪問看護:看護師が自宅を訪問し医療ケアを行う。 | |
| 訪問リハビリ:理学療法士・作業療法士などが自宅を訪問してリハビリを提供する。 | |
| 通所サービス | 通所リハビリ:施設に通い、リハビリ指導を受ける。 |
| 認知症対応型通所介護:施設に通い、食事や入浴などのサービスが受けられる。 | |
| 多機能型サービス | 小規模多機能型居宅介護:通所をメインに、訪問介護、短期宿泊などのサービスが受けられる。 |
| 宿泊サービス | 短期入所生活介護:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの施設に短期宿泊するサービス。 |
| 短期入所療養介護:医療的ケアが必要な方が医療機関や介護老人保健施設などに宿泊するサービス。 | |
| 入居サービス | 特定施設入居者生活介護:指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで日常生活支援が受けられる。 |
| 地域密着サービス | グループホーム:認知症ケア施設で共同生活を送る。 |
| 福祉用具 | 福祉用具貸与:専門業者から福祉用具をレンタルできるサービス。 |
| 特定福祉用具販売:専門業者から福祉用具を購入できるサービス。 |
要介護度ごとに定められた介護保険の支給限度額の範囲なら、自己負担は1割~3割です。介護保険の支給限度額を超過した場合には、全額自己負担になります。
介護予防を目的としたリフォームは介護保険適用になる
上記でご紹介したサービスのほか、要支援認定を受けると介護予防を目的としたリフォームが介護保険適用になります。転倒予防や手すりの設置など、「住宅で不安な箇所」には対策を講じましょう。
とくに検討してもらいたいのは、トイレの交換。足腰が弱くなると、和式トイレでは「用を足しにくい」「膝や股関節に負担がかかる」など、身体に負担がかかります。要支援でも介護保険適用になるため、ぜひ利用を検討してもらいたい箇所です。仮に1割負担の場合には、20万円の工事費が2万円で完了します。
対象となる福祉用具がレンタルできる
要支援の認定を受けると、対象となる福祉用具をレンタルすることができます。「要介護状態の予防のために利用できる福祉用具」が対象で、以下のものがあります。
- 設置工事を伴わない手すり
- 設置工事を伴わないスロープ
- 歩行器、歩行補助つえ
車椅子や特殊寝台、自動排泄処理装置などは「要支援での利用が想定しにくい」ため、原則として介護保険を利用したレンタルはできません。全額自己負担になります。
「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用するという方法も
「予防訪問介護」や「通所介護(デイサービス)」を検討しているなら、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用しても良いでしょう。各自治体が主体となってサービスを提供するため、内容や料金は異なります。一例として以下のものがあります。
- 訪問型・通所型サービス
- 配食
- 見守り
地域によっては、自治体がNPO法人・ボランティア団体を支援して庭木の剪定や移動支援などを行っていることも。介護保険では賄いきれないサービスをカバーしてくれることもあります。
サービスの利用頻度と費用負担額の例
要支援認定を受けた場合のサービスの利用頻度と費用負担額の例を確認しましょう。必要になるサービスは人によってそれぞれなので、あくまでも目安です。
| 要介護度 | サービスの利用頻度と月額費用の目安 | 介護保険支給限度額 |
| 要支援1 | ・訪問型サービス週1回(20,000円~30,000円)
・通所型サービス週1回(20,000円~30,000円) |
50,030円 |
| 要支援2 | ・訪問型サービス週2回(40,000円~60,000円)
・通所型サービス週2回(40,000円~60,000円) |
104,730円 |
自己負担額は1割なので、介護保険支給限度額をめいっぱい使った場合でも、要支援1の方はおよそ5,000円、要支援2の方はおよそ10,000円になります。なお一定以上の所得がある場合には、自己負担額は2割、3割になるため注意が必要です。
要支援認定~サービス利用までの流れ
要支援認定を申請してからサービスを利用するまでを、「申請~結果通知まで」「結果通知~サービス利用まで」に分けてご紹介します。
申請~結果通知まで
要支援認定の申請は、対象となる方がお住まいの市区町村の窓口に依頼しましょう。申請~結果通知までは以下の流れをたどります。
- 訪問調査:認定調査員が訪問して、対象となる方の身体状況・日常生活、家族や住まいなどのヒアリングを行う。
- 主治医の意見書作成:市区町村から主治医に意見書の作成を依頼。かかりつけ医がない場合には、市区町村が指定する医師の診察が必要となる。
- 一次判定/二次判定:一次判定ではコンピュータ判定を行い、二次判定(介護認定審査会)では保健・医療・福祉の専門家が話し合う。
- 結果通知:自宅に認定の結果が郵送される。
正確な判定のためにも、訪問調査ではできる限り細かく対象となる方の状況を伝えましょう。
結果通知後~サービス利用まで
結果通知後、要介護認定に応じた介護保険サービスの利用が可能になります。要支援の判定を受けた方は以下の流れでサービスを受けられます。
- 地域包括支援センターに相談する。
- 地域包括支援センターのスタッフと介護予防ケアプランを作成する。
- サービスを利用する。
要支援の認定を受けた場合には、「地域包括支援センター」に連絡をします。要介護の認定を受けた場合には、「ケアマネジャーがいる市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者」に連絡するため、注意が必要です。
また認定結果には期限があるため、定期更新をしなければなりません。自動更新ではないため、覚えておきましょう。新規の場合は半年間、更新の場合は1年間が有効期限です。
適切な支援を受けて介護予防に努めよう
要支援は、食事や排泄などの日常生活における基本動作が可能な状態です。掃除や洗濯など複雑な動作には手助けが必要なことがありますが、適切な介入をすれば介護を予防できる段階といえます。
「介護保険サービスの利用は抵抗がある」という高齢者もいますが、適切な時期に適切な支援を受ければ、快適な生活を維持することが可能です。上手に介護保険サービスを利用して、より価値ある生活を手に入れましょう。