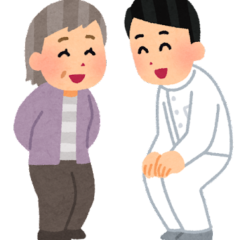介護予防・日常生活支援総合事業を利用して健やかな老後に備えよう
介護予防・日常生活支援総合事業をご存知ですか。「将来に備えて介護予防に努めたい」「一人暮らしだから見守りを強化してほしい」などの声に応えることができる、2015年から開始された比較的新しい取り組みです。
現在全国すべての市区町村でさまざまなサービスが受けられるため、介護予防・日常生活支援総合事業を知ることで、あなたやご家族に適した暮らし方が見つかるかもしれませんよ。本記事では、介護予防・日常生活支援総合事業として提供されるサービス、メリット・デメリット、サービスを受けるまでの手順をご紹介します。
介護予防・日常生活支援総合事業とは65歳以上の高齢者が利用できるサービス
介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・生活支援総合事業」と「一般介護予防事業」に分けられます。市区町村が主体となって、地域住民が参画し支え合う体制づくりを推進します。それぞれ具体的なサービスと内容を見ていきましょう。
サービス1:訪問型・介護型をとる「介護予防・生活支援サービス事業」
「介護予防・生活支援サービス事業」には、以下のサービスがあります。地域住民やボランティアのほか民間企業などが連携して、地域の状況に合わせた訪問型・通所型のサービスを提供します。
訪問型サービス
訪問型サービスは、自宅にサービス提供者が訪問してサービスを提供します。「自立した生活を継続できるように」「身体機能の維持ができるように」など高齢者のニーズに沿った日常生活支援を行います。
入浴や排せつなどの身体介護は介護専門職から提供されますが、掃除や洗濯、料理などの日常生活援助は市区町村の研修修了者が対応し、ゴミ出しや電球交換などはボランティアや民間企業が対応することも。
市区町村によってサービス内容が異なりますが、栄養指導や口腔ケア、運動機能トレーニングなどが専門職から提供されることもあるため、相談窓口に問い合わせてみましょう。
通所型サービス
通所型サービスは、自宅から施設に通って日帰りでサービスを提供してもらうスタイルです。デイサービスを提供する施設を利用して体操やレクリエーションなど、デイサービスに相当する内容が提供されます。
しかしデイサービスは規模によって専門職の人員基準が異なるため、施設・利用時間によっては介護専門職がいないことも。レクリエーションや運動機能訓練などのサービスは提供してくれますが、事業対象者に入浴や食事の提供がない、送迎がないなどのケースも想定されるため、事前にしっかり確認しましょう。
生活支援サービス
生活支援サービスは、市区町村が主体となって独自に提供するサービスです。市区町村によってサービス内容が異なるため、あなたやご家族に適したサービスを提供しているか否かを、相談窓口で問い合わせてみることをおすすめします。
一例としては、栄養改善を目的とした配食サービス、地域ボランティアによる見守りサービスなどです。健康状態の確認や困りごとの対応を提供する市区町村もあり、高齢者の意見が反映されたさまざまなサービスがあります。
介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントは、高齢者の状況に合ったサービスが提供されるよう、地域包括支援センターが介護予防のためのケアプランを作成してくれます。できる限り運動機能を低下させず、健やかな老後を迎えるために以下のポイントを考慮して作成されます。
- 地域と関わり、生きがい・役割を持った生活ができるように支援する。
- 生活の質を維持できるように総合的な支援をする。
- 利用者様が積極的に介護予防に取り組めるよう支援する。
ご本人の目標や希望が明確な場合には、担当者に相談してみましょう。
サービス2:生活機能改善・生きがい作りのための「一般介護予防事業」
一般介護予防事業は、市区町村主体で実施され「介護予防」をメインに行われます。身体機能維持のほか、社会参加による生きがいづくりなど市区町村がボランティアや民間サービスと連携してサービス提供するのが特徴です。
具体的には以下のものがあげられます。
- 体力作り教室
- フレイル予防講習会
- サークル活動
- 介護予防ボランティア養成講座
市区町村によって実施する内容は異なりますが、高齢者が持つ能力を活かした活動や社会参加を促すことによって、地域との関わりを持つことができます。
介護予防・日常生活支援総合事業の対象者は使用するサービスごとに異なる
上記でご説明した通り、介護予防・日常生活支援総合事業には大きく分けて2種類あります。それぞれの対象者は以下の通りです。
| サービス | 対象者 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | ・要支援者
・「基本チェックリスト」で対象者に該当した方 ・要介護者(介護給付を受ける前から介護予防・日常生活支援総合事業を継続的に利用している方) |
| 一般介護予防事業 | ・65歳以上の高齢者 |
「基本チェックリスト」で対象者に該当すれば、要介護認定を受けていない高齢者でも必要なサービスを受けることができます。チェックリストは日常生活や身体状況、外出の頻度など25項目の質問で構成され、対象者の認定は当日~3日程度とスピーディーです。
一般介護予防事業においては、65歳以上の高齢者すべてが対象で、介護給付を受ける前から介護予防・日常生活支援総合事業を継続的に利用している要介護者も含まれます。
介護予防・日常生活支援総合事業が導入された背景
介護予防・日常生活支援総合事業は、介護保険法の一部改正により、平成27年からスタートした事業です。生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加をバックアップする目的で設立され、平成29年には全国の市区町村でサービスが開始されました。
これまでの制度下においても、掃除や料理といった家事支援を提供することは可能でしたが、介護保険給付の増加に伴い財政的に困難になるという背景があり、NPOや民間企業、ボランティアを主体としたサービスを展開していくことになったのです。
今では「地域包括ケアシステム」の事業の一つとして位置づけられ、「自助・共助・互助・公助」をつなぎ合わせ、高齢者が住み慣れた土地で生活することを目標としています。これまで要介護認定に該当しなかった高齢者でも、サービスを受けられることが特徴です。
介護予防・日常生活支援総合事業のメリット・デメリット
まだスタートして日が浅い介護予防・日常生活支援総合事業ですが、次第にメリット・デメリットが明確になってきました。今後は利用者様の声を反映して、制度の改正や変更があるかもしれません。適切に利用するために、今の状況を理解しておきましょう。
メリット:要介護・要支援認定を受けていない方でも利用できる
介護予防・日常生活支援総合事業の最大のメリットは、要介護・要支援認定を受けていない方でもサービスを利用できる点です。基本チェックリストで対象者に該当すれば利用できるため、これまで介護保険利用が出来なかった方も円滑にサービスを受けることができます。
利用者様のニーズに合ったサービスを選択できるため、慣れ親しんだ環境で安定した生活を送ることができます。サービス提供までの時間も早いため、利用者様の「利用したい」気持ちが冷めにくい点もメリットです。
デメリット:提供されるサービスの質と安全性に心配がある
利用者様にデメリットがないと思われる介護予防・日常生活支援総合事業ですが、提供されるサービスの質と安全性に心配があるという声があります。サービス内容によっては必ず資格が必要というわけではないため、サービス提供者全員が介護専門職ではないからです。
さらに介護サービス事業者の視点に立つと、介護保険サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方を提供しなければならないため、仕事量が増加します。それに伴い、サービスの質と安全性という点で心配が生じるわけです、各市区町村によってもサービスの内容が異なるため、格差が起こっていることも想定されます。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスをうけるまでの手順
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けるまでの手順は以下の通りです。
- 地域包括支援センターまたは市区町村の相談窓口に、介護予防・日常生活支援総合事業の利用したい旨を相談する。
- 要支援・要介護認定を受けていない方は、チェックリストで心身の状態を確認する。(結果によって要介護認定の申請を検討)
- チェックリストの介護予防・日常生活支援総合事業の対象者に該当すればサービスを受けられるが、非該当の場合でも65歳以上なら一般介護予防事業のサービスが利用可能。
- 地域包括支援センターにおいてケアプランを作成してもらい、サービスの利用が開始される。
対象者と認定されるまで、当日~3日とスピーディーですが、チェックリストの結果によっては要介護認定の申請がベターと判断されることがあります。時間に余裕を持って相談、申請をしましょう。
介護予防・日常生活支援総合事業を利用して住み慣れた環境で生活しよう
これまでの制度下では、高齢者が安心して生活できる環境を支えることは困難でした。介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者のちょっとした「困った」や「不安」な状況に寄り添い、解決に導くことが可能です。
身体機能の維持だけではなく、高齢者の能力を活かして介護予防を地域で連携して支えることができるため、住み慣れた環境で安心した生活を送ることができます。今後さらなる改正や変更を経て、必要なときに誰もが利用できるサービスに発展することが期待されています。