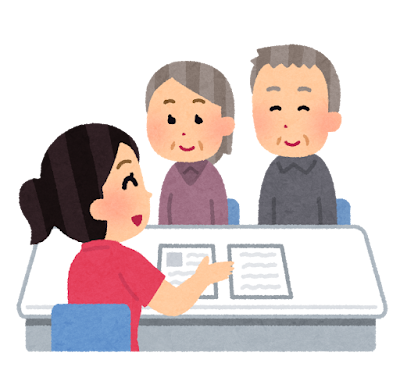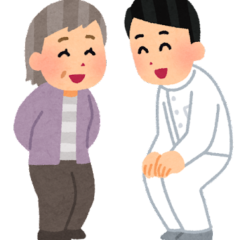グループホームの費用内訳を知って今後必要になる費用を把握しよう
グループホームは、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者などが集団で暮らす施設です。すでに認知症と診断されたご家族がいるなら、グループホームを検討しても良いかもしれませんよ。
今後必要になる費用や具体的に提供されるサービスを知ることができれば、ご本人のニーズに沿った施設を選択することが可能です。
本記事では、グループホームの費用内訳や助成制度を紹介。ご本人の判断能力に不安がある場合の対応についても解説します。グループホームの費用を把握して、施設選択の参考にしてください。
グループホームとは認知症高齢者を対象とした施設
グループホームとは、おもに認知症高齢者が集団で共同生活を送る専用施設です。5~9人の利用者様がユニットとなり、食事・洗濯・掃除などの作業を、スタッフの介助のもと自分たちで行います。
認知症高齢者は新しい環境や人間関係に慣れるまで時間を要する方が多く、ユニットで生活することで毎日馴染みの顔で生活できるため、認知機能を維持する効果が期待されています。
厚生労働省が令和2年7月に作成した資料によると、平成19年は約8,700件だった事業所数は、平成31年で約13,000件と増加傾向です。ニーズに伴って利用しやすい環境になりつつあります。
グループホームの費用内訳
グループホームの費用は、入居時にかかる費用と月額でかかる費用の大きく2つに分けられます。とくに入居時にかかる費用は、0円~100万円と大きな幅が。施設によってかかる費用や提供されるサービスは異なりますが、ここではおおまかな費用体系をご紹介します。
入居時にかかる費用
グループホームに入所する際には、入居時に一時金が必要になることが一般的です。賃貸住宅における「敷金」に近いもので、以下のような特徴があります。
入居一時金(保証金)
グループホーム入居時には、入居一時金や保証金を支払うことがあります。以下、それぞれの特徴をご説明します。
- 入所一時金:施設を利用するための権利を取得するために支払う。具体的な金額が国で定められていないため、施設によってさまざま。入居一時金が必要ない施設も。
- 保証金:退去時の居室清掃や修繕、万が一家賃が滞った際の滞納分として充填される。
その他にも施設によっては、入居申し込み金・施設協力金などの名称で初期費用が加算されることも。償却の対象になるか否かも、入居前に施設に確認しておきましょう。
入居一時金の一部は退去時に返還される
施設に入居一時金を支払った場合には、一部が退去時に返還されることがあります。賃貸住宅の「敷金」と同じで、修繕や清掃、費用の滞納などが生じた場合には、差し引かれる仕組みです。
入居一時金の償却期間や償却率も、入所一時金同様、国で定められていないため施設によってさまざまです。3年以内に全額償却という施設もあれば、十数年という長期間にわたって償却していく施設もあります。償却期間と償却率、償却の対象になる範囲など、入所前に必ず確認しましょう。
毎月発生する費用
入居一時金のほか、毎月発生する費用として、介護サービス費と日常生活費があります。以下、費用の詳細を確認しましょう。
介護サービス費
介護サービス費は、施設内のユニット数、要支援・要介護の状況によって異なります。1ユニットの方がやや割高。厚生労働省のデータによると、1ユニット・1割負担の場合には以下のような標準負担額です。
| 要介護度 | 自己負担額 |
| 要支援2 | 22,800円 |
| 要介護1 | 22,920円 |
| 要介護2 | 24,000円 |
| 要介護3 | 24,690円 |
| 要介護4 | 25,200円 |
| 要介護5 | 25,740円 |
その他、別途以下のような加算が施設によって設けられています。
医療連携体制加算
医療連携体制加算は、看護師を確保することで医療体制を構築し、これまで通り入居者様がグループホームに住み続けられるよう配慮した施設に設けられる加算です。昨今グループホームを退所しなければならない理由の一つである「医療ニーズが増えたため」というケースに対応していて、月額1500円前後の自己負担になります。
看護師が胃ろうの処置や喀痰の吸引などを担うため、グループホームに入所しながら医療サービスを受けることができます。医療連携体制加算は、医師による定期的な診療や協力医療機関との契約のみでは算定が認められておらず、常勤で1名以上の看護師が必要です。
認知症専門ケア加算
認知症専門ケア加算は、国や自治体が実施する認知症ケアに関する専門研修を修了したスタッフが介護サービスを提供する際に付く加算です。月額100円前後の自己負担が生じます。
平成30年度の介護報酬改定で新設された加算で、特養・老健・グループホームなどのほか、訪問サービスも対象になっています。加算を設けているグループホームでは、深い専門知識を持つスタッフがサービスを提供するため、より手厚い認知症ケアを受けることが可能です。入所施設を検討する際には目安にすると良いでしょう。
生活機能向上加算
生活機能向上加算は、2018年の制度改正において新設された加算項目です。加算の要件としては、「認知症対応型共同生活介護計画」を作成して、生活機能を向上させるため運動の機会を設ける必要があります。
計画作成者以外に、理学療法士・作業療法士、医師などの医療専門職が入居者様の身体状況の評価を行うため、多角的な評価が可能です。月額約200円の自己負担が生じますが、リハビリテーションに力を入れたい方、生活機能の向上を期待する方は、施設に確認してみましょう。
日常生活費
日常生活費には、居住費のほか食費や光熱費、娯楽費・理美容費・おむつ代などが含まれます。居住費は賃料ともよばれ、施設ごとの設備や居室の広さ・間取りなどによって変動し、光熱費が含まれている施設も。都市部の方が郊外よりも割高の傾向にあるため、施設の立地条件も確認しましょう。
食費・娯楽費・理美容費・おむつ代などは、利用回数によって変動しますが、あらかじめ料金設定がされているため、事前確認が可能です。娯楽に用いる材料やおむつなどは持ち込みが可能なこともあるため、問い合わせてみましょう。
グループホームで利用できる助成制度
グループホームで利用できる助成制度には以下のものがあります。入居者様が適用になるかを確認してみましょう。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、自己負担金が限度額を超えた場合に適用される制度です。限度額は所得に応じて設定されており、超過した分の金額が戻ってきます。自己負担限度額は、2021年8月時点では、個人の場合は15,000円、世帯の場合には24,600円~140,100円です。
対象となるのは介護保険サービス費の自己負担部分のみで、食費や居住費などは対象外です。一度申請をすれば、二回目以降は限度額を超過する度に支給されますが、支給申請に2年の時効があるため、市区町村の介護保険・医療保険を扱う窓口で相談しましょう。
社会福祉法人実施の利用者負担の軽減制度
運営母体が社会福祉法人の施設の場合には、低所得者向けに負担軽減制度を設けていることがあります。高額介護サービス費とは異なり、入居者様の経済状況によっては食費や居住費などが軽減制度の適用になることも。
実施の有無は施設によって異なり、「住民税非課税世帯である、収入・資産に関する要件を満たす必要がある」などの条件を設けていることがほとんどです。適用になりそうな場合には、入所前に施設に確認しておきましょう。
自治体独自の助成金制度
自治体によっては、グループホーム入所者に助成をしていることがあります。上記社会福祉法人が実施する軽減制度と同様、「住民税非課税世帯である、収入・資産に関する要件を満たす必要がある」などの条件を設けているため、直接自治体に問い合わせてみましょう。
以下のような助成例があります。
- 住民税非課税世帯を対象に、居住費の一部として月額上限20,000円まで助成。
- 低所得者を対象に日額1,000円助成。
自治体が助成金制度を設けている場合でも一律ではなく、内容や金額、日額/月額はそれぞれ自治体によって異なります。
本人任せが不安なら成年後見人制度を検討する
グループホームを探す状況にあるなら、入居者様が今後認知症を理由に判断力が低下することも考えられます。なかでも家族がもっとも心配するのは、施設に関する手続きや費用のことです。本人任せが不安なら、成年後見人制度を検討してみましょう。
成年後見人なら施設入所の手続きが可能
成年後見人を選定していれば、成年後見人による施設入所の手続きのほか、財産管理や契約行為が可能です。成年後見人に就任するにあたって、欠格事由がない限り特別な資格は必要ないため、家族や親族が就任することも多くあります。
本人の身体状況が良好な場合には、任意後見人といって本人に成年後見人を指名してもらうことが可能ですが、必要性が生じてからだと、家庭裁判所から法廷後見人を選定してもらうことになります。グループホームへの入所を検討する段階で、あらかじめ選任手続きを済ませておくとスムーズです。
家族の不要なトラブルを防げる
成年後見人を選任すれば、施設入所の手続きのほか、不動産や預貯金の管理が可能になり、以下のようにトラブルを回避できる可能性があります。
- 被後見人が不利益になる契約を前もって防ぐことができる。
- 万が一被後見人が不利益な契約を結んだ場合でも、後から解消が可能。
- 被後見人が亡くなった場合、財産を把握できる。
認知症状は悪化をすると判断能力が欠如することがあるため、成年後見人を選任することでさまざまなシーンから被後見人の財産を守ることができます。
グループホームの費用・助成制度を理解して適切な施設を選ぼう
グループホームには施設によって入居一時金が必要な場合・必要ない場合があり、金額の設定も幅があります。介護サービス費や居住費・食費などの月額費用はどの施設でもかかるため、一時金とあわせて事前にシミュレーションしてみましょう。
入所施設の選定をする際には、費用はもちろん助成制度・成年後見制度も一緒に確認・検討しておくと安心です。無理のない費用負担で、本人・家族が納得したケアを受けられる施設を選びましょう。