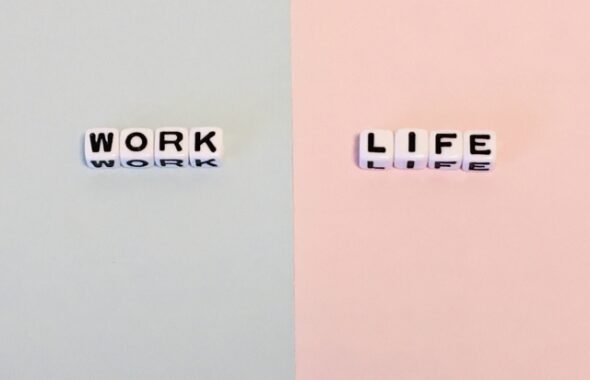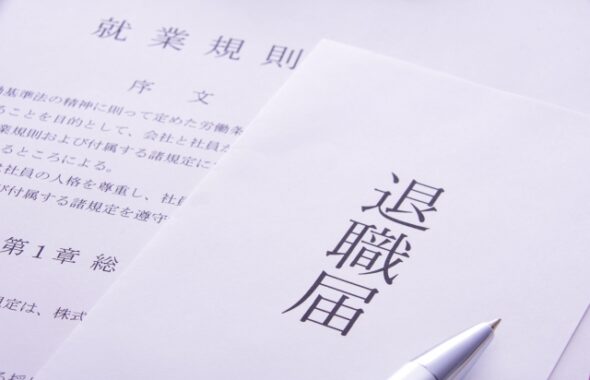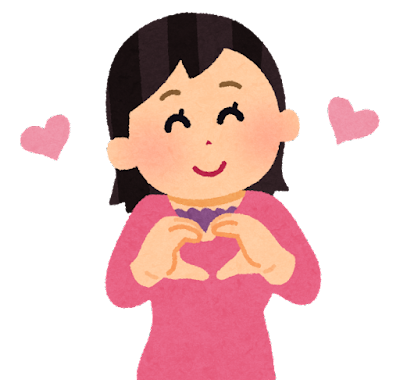居宅療養管理指導はどんなサービスが受けられる?利用方法や費用も解説
「居宅療養管理指導ってどんなサービス?」
「居宅療養管理指導では何をしてもらえるの?」
居宅療養管理指導は、自宅療養している方に向けたサービスですが、サービス内容についてよくわからない方がいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、居宅療養管理指導は医師などによる自宅への訪問指導であること、利用するメリットやデメリット、利用方法などを解説します。
サービス内容について理解して、体のことで困ったときに相談できるようにしましょう。
居宅療養管理指導とは専門職による在宅への訪問指導
居宅療養管理指導とは、要介護状態になった方が、自宅での生活を続けられるように、医師や薬剤師などの専門職が自宅に来て、相談にのってくれるサービスです。
利用がおすすめの人、訪問してくれるスタッフ、利用対象者などについてご紹介しましょう。
自宅で専門家にアドバイスしてほしい方が利用する
居宅療養管理指導は病院に通院するのが難しい、以下のような方に役立ちます。
- 1人暮らし
- 老老介護
- ご本人や家族Kだけだと薬や栄養管理ができない
- 家族の手が回らない
ご本人と接する機会が多いヘルパーとも情報共有してアドバイスしてもらえるため、日常生活での困りごとに合ったアドバイスがもらえます。
居宅療養管理指導は訪問介護サービスであるため、利用したい場合にはケアマネジャーに相談しましょう。
訪問するスタッフとサービス内容
居宅療養管理指導で、訪問できるスタッフは、医師や歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士です。それぞれの職種とサービス内容を表にまとめました。
| 職種 | サービス内容例 |
| 医師、歯科医師 |
|
| 薬剤師 |
|
| 栄養士 |
|
| 歯科衛生士 |
|
(参考:社保審ー介護給付費分科会「居宅療養管理指導」)
体が動きにくくて通院できない方でも、希望する専門職が自宅に訪問して指導してくれるので、気軽に相談ができます。
医師や歯科医師は、往診と同じ日に行うことになっているため、往診の前後に行われることも多いです。体のほかにも、在宅サービスなどについて相談できます。
薬剤師は薬の管理や指導をしてくれます。残薬確認や飲み忘れを防ぐ方法などを相談できるため、薬の適正な使用のために有効です。実際、訪問薬剤師の指導した際の、残薬の発見に関する多数の報告があります。
平成27年10月に訪問した在宅患者のうち、226人に残薬が発見され、そのうち43%は大量の残薬を認め、23%には認知症が疑われたとの報告がありました。在宅では、薬の管理がうまくできていない方が多いといえます。居宅療養管理指導を利用すれば、服薬ミスを防ぎやすくなるでしょう。
栄養士は、自宅の調理場で食事形態や献立のアドバイス、栄養量の相談にのってくれます。高齢で食事量が減ったり飲み込みの力が落ちた方にすすめられます。
歯科衛生士は自宅に訪問して口腔内の管理を手伝ってくれます。サービス内容についての調査結果では、ほぼ毎回実施するものとして多い順に口腔ケア(95.8%)、義歯の状態評価(60.4%)、義歯の清掃方法の指導(56.%)などがあがりました。
このように、居宅療養管理指導と一言で言っても、さまざまな職種の多様なサービスが受けられるといえます。
(参考:厚生労働省「居宅療養管理指導」)
要介護1以上の方が対象
居宅療養管理指導の対象者は、要介護1以上と認定された方です。
「要支援だとだめなの?」と疑問に思うかもしれませんが、要支援の方には「介護予防居宅療養管理指導」という名前の似たようなサービスがあるため、そちらを利用しましょう。
居宅療養管理指導の費用は?
居宅療養管理指導における費用の特徴を示します。
- 介護保険サービスに準じて1割~3割負担
- 訪問1回約300円~550円
居宅療養管理指導の費用は、実際にかかった金額の1割(一部高所得者の方は2~3割)の負担ですみます。残りの費用は、介護保険からの補助です。
介護保険サービスには、要介護度の重さに応じて、毎月利用できる金額に上限が決められていますが(支給限度額)、居宅療養管理指導は支給限度額とは別に設けられています。介護保険サービスを上限金額ぎりぎりまで使っていても利用できるので、ご安心ください。
居宅療養管理指導に関する費用の目安を表にまとめました。
費用は、居宅療養管理指導を、同じ建物に住む人が、何人同じ月に利用するかによって異なります。たとえば、小規模多機能型住居や老人ホームなどの集合住宅で複数人が利用する場合には、1回の訪問費用が安くなります。
居宅療養管理指導の費用の目安(1割負担の方の場合)
| 訪問するスタッフ | 同じ建物内で同じ月に居宅療養管理指導を利用する人数 | |||
| 1人 | 2~9人 | 10人以上 | ||
| 医師 | 514円 | 486円 | 445円 | |
| 歯科医師師 | 516円 | 486円 | 440円 | |
| 薬剤師 | 病院や診療所の薬剤師 | 565円 | 416円 | 379円 |
| 薬局の薬剤師 | 517円 | 378円 | 341円 | |
| 管理栄養士 | 544円 | 486円 | 443円 | |
| 歯科衛生士 | 361円 | 325円 | 294円 | |
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」)
どの職種も、月に訪問できる回数に、以下のように制限があります。医師は月2回までです。
| 訪問スタッフ | 訪問回数の限度 |
| 医師
歯科医師 管理栄養士 病院や診療所の薬剤師 |
月2回まで |
| 薬局の薬剤師
歯科衛生士 |
月4回まで |
訪問する職種によって、訪問できる回数や費用が異なる点については抑えておきましょう。
居宅療養管理指導のメリット
実際、居宅療養管理指導を使うと何がいいの?と疑問に思う方に向けて、居宅療養管理指導のメリットをご紹介します。
- 病院に行かなくても栄養や体調の管理ができる
- 通院の手間が減る
- 利用者や家族の負担軽減
- 専門家から適格なアドバイスがもらえる
最大のメリットは、通院せずに自宅で専門家の指導が受けられる点です。
体が不自由な方にとっては、ベッドから車いすに移動してタクシーに乗り、病院に行くのは大変です。居宅療養管理指導であれば、自宅に来てもらえるので、移動の際のご本人やご家族の負担がなくなります。
また、通えないからといって、専門家に相談せずに不調をそのままにして長期間過ごすのもおすすめできません。介護が必要な方は、体調をくずしやすいものです。ちょっとした不調でも、相談せずに我慢していると、思わぬ体調不良につながることがあります。
気になる症状があったら早めに専門家に相談することで、薬や体、歯、食事などの、健康にかかわる大切な部分を整えられるのです。
また居宅療養管理指導は、ご家族の負担も軽減できます。
ご家族は日々の介護だけでも大変なものです。健康から食事、薬の管理まで、すべてご家族だけで整えるのは負担が大きすぎるといえるでしょう。
居宅療養管理指導であれば定期的に専門家のチェックや指導が受けられるので、おまかせできます。
居宅療養管理指導のデメリット
一方、居宅療養管理指導にはデメリットもあります。
- 利用回数に制限がある
- 医療行為は受けられない
- 医師か歯科医師の指示が必要
居宅療養管理指導の利用は、上限回数が決まっています。何回でも受ける、とはいかない点に注意しましょう。
また、居宅療養管理指導はあくまでも「指導」です。医師の訪問でも、薬の処方や診察などは受けられません。
ただし、医師や歯科医師による居宅療養管理指導は、訪問診療や往診の利用者が対象で、「診察と同じ日に行う」との決まりがあります。基本的には、往診や訪問診療の前後で連続して行われることが多いため、診察と指導はセットのパターンが多いといえます。
また、居宅療養管理指導を利用するときには、医師か歯科医師の指示が必要です。医師が必要と判断することでサービスが受けられることも抑えておきましょう。
居宅療養管理指導と往診や訪問診療との違い
ここまで読むと「結局、居宅療養管理指導は往診や訪問診療とはどう違うの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。
居宅療養管理指導と往診、訪問診療は、どれも医師が自宅に訪問するサービスです。サービス内容や使用する保険など、異なる点について説明します。
サービス内容の違い
居宅療養管理指導と往診、訪問診療との違いについて、ご説明します。
居宅療養管理指導は、あくまでも「指導」「アドバイス」が中心で、薬の処方や診察といった医学的処置が行えません。
一方、往診と訪問診療は、以下のように医学的処置が行えます。
| サービス内容 | |
| 訪問診療 |
|
| 往診 |
|
(参考: 日本訪問診療機構「訪問診療と往診の違い 」)
訪問診療は、定期スケジュールが組まれている診察です。定期的に病院に通うのと同じように、決まったスケジュールで診察が受けられます。
一方往診は、突発的な診察です。突然の発熱や体調不良などで、救急車を呼ぶほどではないけれど診察を受けたい際に依頼します。
往診も訪問診療も、薬の処方や検査、診察などが行えます。
使用する保険の違い
居宅療養管理指導と往診・訪問診療が使用する保険、表に示します。
| サービス | 使用する保険 |
| 居宅療養管理指導 | 介護保険 |
| 往診 | 医療保険 |
| 訪問診療 |
往診や訪問診療と異なり、居宅療養管理指導は介護保険のサービスです。そのため、あくまでも「指導」にとどまり、医学的な処置が受けられません。
ただし、居宅療養管理指導は「訪問診療又は往診を行った日に限る」との決まりがあります。つまり、居宅療養管理指導は、基本的に往診や訪問診療を受けている方のためのサービスです。
実際は、訪問診療や往診などの診察前後の時間に、連続して行われることが多いでしょう。
居宅療養管理指導の利用方法
居宅療養管理指導のサービスを利用したい方に向けて、利用方法を説明します。
居宅療養管理指導は介護保険のサービスのため、利用するまでの基本的な流れは以下の通りです。まずは介護保険で要介護認定されていることが利用条件です。要介護認定の申請をしていない方は、先にすませておきましょう。
- ケアマネジャーや医師に居宅療養管理指導を受けたいと希望する
- ケアマネジャーが訪問してくれる医師や専門家、事業者をさがす
- 契約する
居宅療養管理指導はケアマネジャーに相談したうえで、医師の指示が必要です。
要介護認定については、以下のサイトをご覧ください。
→要介護認定とは?要介護度別の特徴とサービス利用までの流れをご紹介
居宅療養管理指導のサービスについて知って必要な専門職の指導を受けよう
居宅療養管理指導は、医師などの医療専門職が、自宅に訪問して指導してくれるサービスです。要介護で通院が難しい方の医学管理に役立ちます。
利用にあたっては要介護認定されている必要があるため、要介護認定の申請をしていない方はまずは申請しましょう。
認定されたらケアマネジャーに希望すると、サービスを利用できます。積極的に活用して、自宅での食事や薬、健康、歯などさまざまな管理にお役立てください。