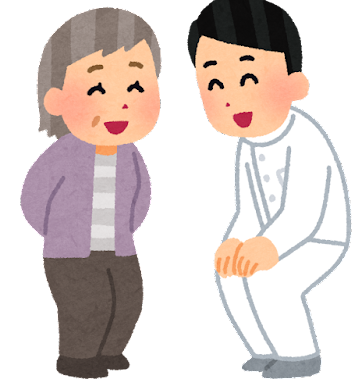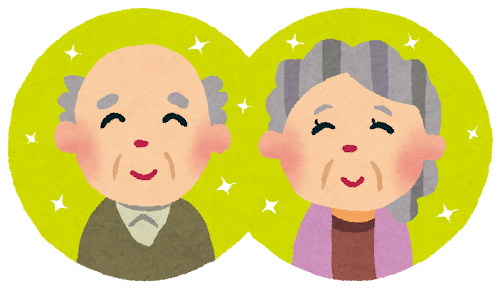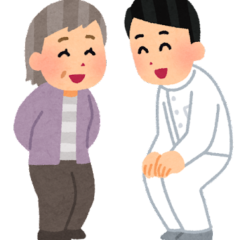小規模多機能型居宅介護のメリットを理解して人生の選択肢を広げよう!
在宅介護をしながらデイサービスやショートステイをそれぞれ利用すると、手続きが煩雑です。利用者が環境に適応するまで時間もかかるため、家族・利用者双方にとって負担になることがあるでしょう。
これらの悩みを解決してくれるのが小規模多機能型居宅介護です。平成18年に誕生した新しいサービスですが、慣れた環境で手厚いサービスを受けられるため注目を集めています。
ここでは、小規模多機能型居宅介護についてのメリットや他のサービスとの違いをご紹介します。必要なサービスを上手に取り入れて、その人らしい人生を送れるようにしましょう。
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護の特徴をご紹介します。料金や利用対象者など基本的な部分を抑えましょう。
「通所」「訪問」「宿泊」の3つのサービスが受けられる
小規模多機能型居宅介護とは、「通所」「訪問」「宿泊」の3つのサービスを組み合わせて利用できます。これまでの介護サービスは、利用者の状況に応じて必要なサービスをそれぞれ契約するものでした。
小規模多機能型居宅介護では1つの介護事業者と契約すれば、3つのサービスを提供してくれるため、慣れた環境で日常生活の支援・機能訓練を受ける事ができます。
利用者の状況が変わっても新たにサービスを契約する必要がなく、これまでの人間関係を維持しながら生活できる、それが小規模多機能型居宅介護です。
月額料金で何度でも利用が可能
小規模多機能型居宅介護は、月額料金で何度でも利用できます。単体のサービスを契約した場合には、当然それぞれに費用が発生していました。
小規模多機能型居宅介護の月額費用は介護度によって異なりますが、介護保険支給限度基準額内で、10,000円~100,000円です。食事や日用品、おむつ代などは別途必要になるため覚えておきましょう。
利用に回数制限はありませんが、法律上事業所の登録人数29名以下、通所は18名以下、宿泊は9名以下という定員数があり、当施設では現状、登録人数25名、通所は15名、宿泊は7名以下で運営しております。
要支援1~2、または要介護1~5認定の人が利用できる
小規模多機能型居宅介護は、要支援1~2、または要介護1~5認定の人が利用できます。さらに小規模多機能型居宅介護は、「地域密着型サービス」に属するため、施設がある市町村に住む人という利用条件があります。
また小規模多機能型居宅介護を利用すると、一般的な「通所」「訪問」「宿泊」サービスは利用できません。利用者の状況に応じた断続的なサービスを提供するため、これまでのケアマネジャーから事業所専属のケアマネジャーに変更しましょう。
なお、訪問看護や在宅療養管理指導などの医療サービス、福祉用具貸与や住宅改修などのサービスは併用して利用可能です。
小規模多機能型居宅介護のメリット
小規模多機能型居宅介護はメリットが多く、自分が求めるサービスを受けられることがありますよ。
生活に合ったサービスを利用できる
小規模多機能型居宅介護は生活に合ったサービスを利用することができます。単体のサービスを利用していた場合には、それぞれのルールに則り、事前の予約が必須でした。
小規模多機能型居宅介護なら、通所からそのまま宿泊ができたり、緊急時に訪問をお願いできたり、利用者の体調や環境の変化に柔軟に対応することができます。
回数や時間の制限がない点でも、利用者に寄り添ったサービスが提供できるのです。まさにニーズに沿ったサービスが提供されるため、利用者はもちろん家族の支えになることでしょう。
新しいサービスでも利用者が受け入れやすい
新しいサービスでも利用者が受け入れやすい点も、小規模多機能型居宅介護のメリットです。年齢を重ねると、環境の変化や新しい事を受け入れるまで時間がかかる人もいるでしょう。
とくに認知や心の病を持つ人の場合、通所では落ち着いて過ごせても、初めて宿泊を利用する時に取り乱してしまうことがあります。小規模多機能型居宅介護は、慣れた通所施設で宿泊ができるため、落ち着いて利用ができるのです。
また、スタッフ間で「食欲がなかった」「口数が少なかった」など、利用者の様子を共有できるため、よりきめ細かなサービスが提供できます。
どのサービスでも顔なじみのスタッフが対応してくれる
利用者にとって、常に顔なじみのスタッフが対応してくれる小規模多機能型居宅介護は心強く感じるでしょう。よく知っている関係だからこそ、不安や疑問も気兼ねなく話すことができます。
スタッフも利用者がどのような性格なのか、趣味や好き嫌いを把握しているため、通所・訪問・宿泊どのサービスを利用しても、利用者の立場に沿った判断ができるのです。
「通所施設には行くけれど、宿泊は拒否される」「スタッフの好き嫌いが激しい」などの問題も、小規模多機能型居宅介護なら解決できることがあります。
それぞれのサービスと小規模多機能型居宅介護の違いを紹介
小規模多機能型居宅介護のメリットが分かったところで、単体のサービスとの違いを比較してみましょう。
| 小規模多機能型居宅介護 | 単体サービス | |
| 通所 | 必要なサービスのみの利用が可能 | 1日を通しての利用が一般的 |
| 訪問 | 利用者ごとに時間・内容を決められる | 訪問の時間・内容が決まっている |
| 宿泊 | 緊急時でも利用が可能 | 事前の予約が必要 |
小規模多機能型居宅介護は「通所」をスポットで利用できる
通所とはデイサービスを指します。単体サービスにおいては、施設が決めた時間割に沿って行動するため、1日を通して利用する事が一般的です。
一方小規模多機能型居宅介護の通所は、「入浴だけ」「食事だけ」など、数時間だけの利用が可能です。「1日いるのは辛い」「好きな時間だけ利用したい」など柔軟に対応できるため、「必要なサービスだけ」を受けることができます。
小規模多機能型居宅介護は「訪問」でも時間を気にしなくて良い
訪問はホームヘルプの事です。単体サービスにおいては、身体介護〇分と時間・内容が決められているため、自分のタイミングに合わせてもらうことは難しいでしょう。
一方小規模多機能型居宅介護の訪問は、身体介護のほか、服薬の介助・安否確認など時間を気にせず柔軟な対応が可能。緊急時も駆けつけてくれるため、家族にとって頼りになるサービスです。
「通所」で利用した施設に「宿泊」が可能
宿泊をするショートステイは、単体で利用する場合には事前の予約が必要です。家族が一日中家を空ける場合には、通所と宿泊別々に予約をしなければなりません。
小規模多機能型居宅介護の宿泊は、日中通所していた施設にそのまま宿泊することができます。新たな予約の必要がなく、利用者は同じ場所でサービスを受けられるため、気軽に利用できるでしょう。家族の急用や急病などの場合にも対処可能です。
小規模多機能型居宅介護の利用者の一日
小規模多機能型居宅介護の利用者は、どのような一日を過ごすのでしょう。一例をご紹介します。
| 通所 | 通所+宿泊 | |
| 9:00 | お迎え | お迎え |
| 10:00 | 施設到着、レクリエーションに参加 | 施設到着、レクリエーションに参加 |
| 11:00 | 入浴 | 入浴 |
| 12:00 | 昼食 | 昼食 |
| 13:00 | 昼寝、休憩 | 昼寝、休憩 |
| 14:00 | 体操、おやつ | 体操、おやつ |
| 15:00 | 機能訓練 | 機能訓練 |
| 16:00 | 送迎 | イベントの準備(折り紙や塗り絵など) |
| 17:00 | – | 夕食 |
| 18:00 | – | 仲間と談話 |
| 20:00 | – | 着替え・水分補給 |
| 21:00 | – | 就寝 |
出かける前の身支度や食事の支援が必要な人は、訪問サービスを受けることができます。機能訓練は、スタッフと一緒に食事の準備や片付け、洗濯物を畳むなどの作業も行います。
サービスを受けるためには
小規模多機能型居宅介護を利用するには、担当のケアマネージャーに相談しましょう。現状在宅介護サービスを受けていない場合には、地域包括支援センターが相談窓口です。
介護サービスを受けるのが初めての場合はスムーズに利用できますが、担当のケアマネージャーがいる場合には、小規模多機能型居宅介護を受ける施設のケアマネージャーに変更が必要です。
ヘルパーやデイサービスなど利用するサービスがある場合は、小規模多機能型居宅介護と併用できないため、一旦サービスを終了しましょう。
必要なサービスを受けてその人らしい人生を
小規模多機能型居宅介護とは、通所・訪問・宿泊を必要に応じて利用できる便利なサービスです。顔なじみのスタッフが臨機応変に対応してくれるため、利用者も安心して受け入れてくれるでしょう。
小規模多機能型居宅介護なら家族の負担を最小限にできるだけではなく、顔なじみが集うことでコミュニケーションが活発になり、より生き生きとした人生を送ることができますよ。