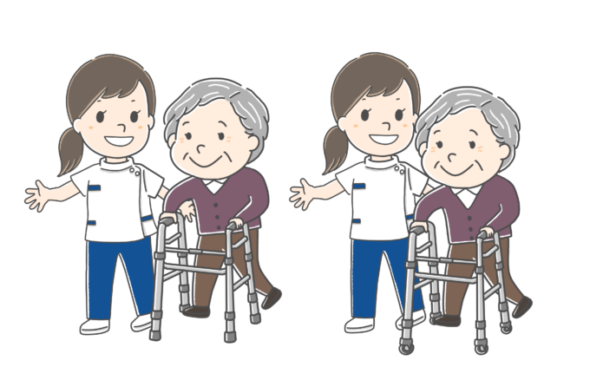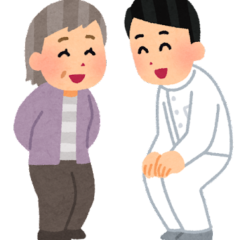介護にかかる費用を知って家族みんなで介護方針・費用を決定する方法
親に介護が必要になったとき、事前に介護費用や介護方針について熟知している家族は少ないでしょう。「介護にいくら必要か」「誰が介護をするのか」疑問が多い中で「決定していく」作業は、困惑することがあります。
「もしかしたら介護が必要になるかもしれない」段階で家族みんなで話し合っておくと、いざというときに落ち着いた行動を取ることができるでしょう。本記事では、具体的な介護費用と期間、介護が必要になったときの費用準備方法までを解説します。
介護にかかる費用と期間
介護にかかる費用・期間は人によってそれぞれ異なりますが、ここではあえて平均的な数値を確認してみましょう。要介護者に「どれくらいの介護を提供すればよいか」の参考になります。
月々の介護費用は平均8.3万円
公益財団法人・生命保険文化センターが令和3年度に行った調査によると、月々の介護費用は平均8.3万円というデータがあります。「過去3年間に介護経験がある人」に調査をしているため、物価・経済状況ともに直近のデータです。
しかしこの8.3万円というのは、一時的に必要になる住宅改造や介護ベッドの購入などの費用は含まれていません。要介護者の身体状況を確認し、「介護になにが必要か」を把握して、準備する必要があります。
介護費用の自己負担額は「介護保険負担割合証」で確認する
介護費用の自己負担額は、「介護保険負担割合証」で確認しましょう。介護保険負担割合証は、介護保険の認定結果と一緒に発行され、毎年7月に更新されます。
自己負担額は、「前年の年金収入+その他所得」から「控除や必要経費」を差し引いた金額で決定され、遺族年金や障害者年金は含まれません。一般的に自己負担額は1割ですが、所得が多い要介護者は自己負担額が3割になることも。65歳以上の一人暮らしの方の場合は「前年の年金収入+その他所得」が年間340万円以上の収入がある場合、3割負担になります。
介護期間は平均5年1ヶ月
公益財団法人・生命保険文化センターが令和3年度に行った調査によると、介護期間は平均5年1ヶ月という結果でした。3年未満と回答した方が32.8%である一方で、10年以上と回答した方が17.6%います。
4年以上という期間で見てみると、約半数が該当するため、介護者は長い期間にわたって介護を提供していることが伺えます。これらのことからも、施設や介護サービスを上手に利用し、メインとなる介護者に負担がかからないよう、兄弟姉妹が協力する必要があるのです。
それぞれのサービスごとの自己負担額例
介護費用と介護期間の「平均」を確認したところで、具体的な自己負担額をみてみましょう。それぞれの金額のほか、施設ごとに変化する金額・特徴も確認してください。施設入所・在宅介護に分類してご紹介します。
施設入所のケース
今回は、利用を検討されることが多い特別養護老人ホーム・介護付き有料老人ホーム・グループホームの自己負担額の具体例をご紹介します。
特別養護老人ホームの費用は部屋のタイプで異なる
特別養護老人ホームは、部屋のタイプで費用が異なります。一般的には要介護3以上の方が対象で、介護保険適用で生活支援のほか、機能訓練などのサービスを受けることができます。
| 部屋のタイプ | 30日計算の自己負担額 |
| ユニット型個室 | 60,180円 |
| ユニット型個室的多床室 | 50,040円 |
| 従来型個室 | 35,130円 |
| 多床室 | 25,650円 |
*自己負担額1割の方を想定して計算しています。
地域によって異なりますが、市区町村民税課税世帯を対象とした方の一例です。別途、施設によって、食費やサービス加算費用などがかかります。
介護付き有料老人ホームやサ高住・ケアハウスは「上乗せ加算」をチェック
介護付き有料老人ホームやサ高住・ケアハウスなどは、「上乗せ加算」をチェックしましょう。入所後の介護サービス費用は定額ですが、施設によっては「手厚い人員体制をとっている」「医療体制を充実させている」場合があります。
| 要介護度 | 30日計算の自己負担額 |
| 要支援1 | 5,460円 |
| 要支援2 | 9,330円 |
| 要介護1 | 16,140円 |
| 要介護2 | 18,120円 |
| 要介護3 | 20,220円 |
| 要介護4 | 22,140円 |
| 要介護5 | 24,210円 |
*自己負担額1割の方を想定して計算しています。
上記は一例ですが、施設によっては入居一時金が発生することもあるため、事前に施設に確認しておく事をおすすめします。
グループホームはユニット数で若干費用が異なる
グループホームは、認知症の方が入所する施設です。グループホームに入所するとユニットの一員として、アットホームな環境下で生活することになります。施設と同じ地域に住民票を持っていること、要支援2あるいは要介護1以上、さらに医師による認知症の診断が必要です。
| 要介護度 | 1ユニット | 2ユニット |
| 要支援2 | 22,800円 | 22,440円 |
| 要介護1 | 22,920円 | 22,560円 |
| 要介護2 | 24,000円 | 23,610円 |
| 要介護3 | 24,690円 | 24,330円 |
| 要介護4 | 25,200円 | 24,810円 |
| 要介護5 | 25,740円 | 25,320円 |
*自己負担額1割の方を想定して、30日計算で自己負担額を計算しています。
わずかではありますが、2ユニットの方が割安です。事前に施設を訪問・見学し、それぞれの雰囲気をつかんでおくと良いでしょう。
在宅介護のケース
在宅介護の場合には、訪問介護や通所介護などから必要なサービスを選択することになります。利用する際には、契約した事業所のケアマネージャーに「ケアプラン」を作成してもらわなければなりません。それぞれ介護サービスの自己負担額を確認していきましょう。
通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア)は利用時間で費用が異なる
通所介護・通所リハビリは、生活支援のほか、リハビリやレクリエーションなどを提供してくれるサービスです。日帰りのサービスで、希望や条件が整えば、自宅から施設まで送迎もしてくれます。以下通所介護の自己負担額例です。
| 要介護度 | 1回ごとの自己負担額 | ||||
| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | |
| 要介護1 | 368円 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 |
| 要介護2 | 421円 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 |
| 要介護3 | 477円 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 |
| 要介護4 | 530円 | 557円 | 876円 | 897円 | 1,018円 |
| 要介護5 | 585円 | 614円 | 979円 | 1,003円 | 1,142円 |
*自己負担額1割の方を想定して計算しています。
要介護度が上がり、利用時間が増えるにつれて自己負担額も上がります。「宿泊や入所までは必要ないけれど、介護者・要介護者のリフレッシュに」と利用するご家族も多くいます。なお通所リハビリ(デイケア)の方が医療介入ができるため、150円~300円ほど割高です。
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)の費用は部屋タイプで異なる
短期入所生活介護・短期入所療養介護においては、数日~2週間程度の利用が想定されており、部屋のタイプによって費用が異なります。以下、短期入所生活介護の自己負担額例を確認してみましょう。
| 部屋のタイプ | 1日計算の自己負担額 | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| ユニット型個室 | 738円 | 806円 | 881円 | 949円 | 1,017円 |
| ユニット型個室的多床室 | 738円 | 806円 | 881円 | 949円 | 1,017円 |
| 従来型個室 | 638円 | 707円 | 778円 | 847円 | 916円 |
| 多床室 | 638円 | 707円 | 778円 | 847円 | 916円 |
*自己負担額1割の方を想定して計算しています。
従来型個室・多床室よりもユニット型個室・ユニット型個室的多床室の方がやや割高です。利用期間を考慮しながら、快適に過ごせる部屋タイプを選択しましょう。なお短期入所療養介護の方が医療介入ができるため、150円~300円ほど割高です。
訪問介護はサービスの内容・時間で費用が異なる
訪問介護においては、サービスの内容・時間で費用が変動します。以下、訪問介護の自己負担額例です。訪問する介護スタッフが、どのような介護サービスを提供するかに注目して費用を確認してみましょう。
| サービス内容 | 所要時間 | 1回計算の自己負担額 |
| 身体介護 | 20分未満 | 167円 |
| 20分~30分 | 250円 | |
| 30~60分 | 396円 | |
| 60分以上 | 579円 | |
| 生活援助 | 20~45分 | 183円 |
| 45分以上 | 225円 | |
| 移乗介助 | – | 99円 |
*自己負担額1割の方を想定して計算しています。
訪問介護を依頼する際には、要介護者に必要なサービス内容をケアマネージャーと相談しましょう。訪問看護も訪問介護同様、所要時間によって自己負担額が変化します。訪問入浴や訪問リハビリテーションは1回あたりの計算です。
介護費用はどうする?
介護にかかる費用を把握したところで、今後どのように介護費用を工面したら良いかをご説明します。以下の手順で進めると、介護の方向性が明らかになるため、手続きやサービスの選択がスムーズです。
ステップ1:要介護者・配偶者の資産を把握する
まず、要介護者・配偶者の資産を把握しましょう。介護にかかる費用は、要介護者本人か配偶者の資産から捻出することが一般的です。以下のものを確認しましょう。
- 要介護者が保有する銀行口座
- 株式・投資など有価証券の有無
- 生命保険の契約の有無
- 不動産の有無
- 年金収入の状況
2019年の厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、要介護者・配偶者以外の収入・貯蓄を介護費用に充てているケースは、1割弱というデータがあります。しかし要介護者の経済状況や希望する介護サービスによっては、子が負担する可能性もゼロではありません。負債状況もあわせて確認することを忘れずに。
ステップ2:資産をもとに介護方針を決定する
要介護者の資産が明らかになったら、介護方針を決定しましょう。介護者はもちろん、要介護者の意見を聞くことも忘れずに。以下のような内容を具体的にしておくと、施設やケアマネージャーに相談するときにスムーズです。
- 施設入居を希望するか、在宅を希望するか。
- 子ども達と交流を持ちたいか否か。
希望する施設や介護サービスによって、費用や介護に充てられる時間が異なります。介護者・要介護者が望む介護生活をイメージしてみましょう。
ステップ3:メインで介護する人や資産管理人を決定する
介護方針が決定したら、メインで介護する人や資産管理人を決めましょう。要介護者の身体状況によっては、以下のような役割も担うため、24時間付き添いが必要だったり、駆けつけられる距離で介護者が生活したりといった環境が必要です。
- かかりつけ医やケアマネージャーとのやり取りをして、スケジュール管理を担う。
- 施設契約時や入院時の保証人・連帯保証人になる。
メインの介護者に負担が偏らないよう、協力できる兄弟姉妹がいる場合には、積極的に介護に関わってもらいましょう。「週末は介護ができる」「介護休暇を取得できる」など、それぞれの状況を家族みんなで共有しておく必要があります。
ステップ4:費用の不足分を兄弟で相談しておく
要介護者の収入・貯蓄だけでは費用が十分ではない場合、不足分をどうするのかを事前に兄弟姉妹で相談しておきましょう。家庭によって経済状況は違いますが、以下のポイントをおさえて話し合うと、具体的な金額が明確になります。
- 不足分は兄弟姉妹で均等に折半する。
- 遠方で介護に関われない場合には、多めに費用を負担する。
また要介護者を扶養親族とすれば、扶養控除や身体状況によっては障害者控除が受けられることも。施設の支払いや要介護者に必要な日用品など、家族みんながお金の出入りを確認できる公平性を保ちましょう。
介護費用・分担は兄弟姉妹で事前に話し合いをしておくと安心
介護費用・分担は兄弟姉妹で事前に話し合っておくことをおすすめします。誰か一人に負担が偏ると、トラブルに発展する可能性があります。親に穏やかな老後を送ってもらうためにも、「自分が原因で子ども同士が争っている」という事態は避けなければなりません。
家族とはいえ、考え方が違うのは当たり前。お互いに少しずつ歩み寄り、さまざまな介護サービス・費用をもとに、できる限り親の意向に沿った介護サービスを選択してあげましょう。