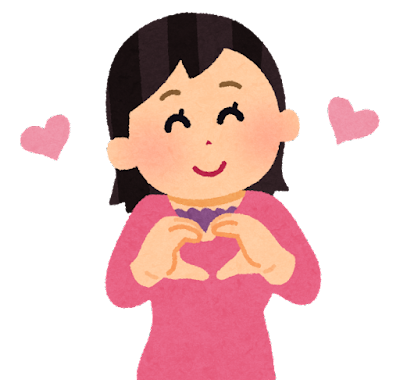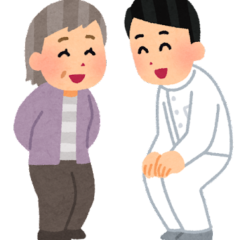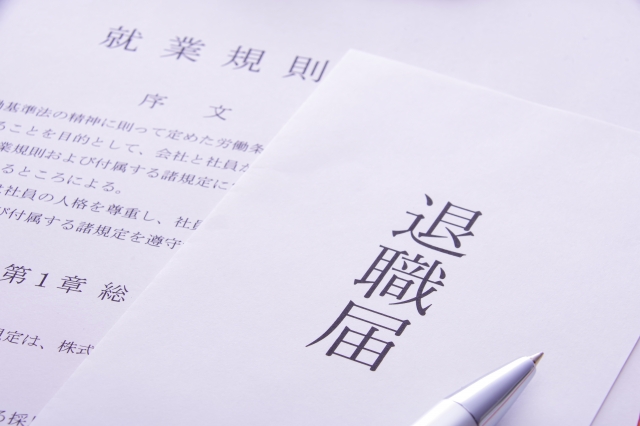
介護で退職を考えた時に知っておきたい現実と退職前の打開策
ご家族に介護が必要になって、「退職」を考えてはいませんか?「介護に集中したい」「職場に迷惑をかけたくない」などの理由から早急に退職すると、時間的余裕ができる一方で、金銭的・精神的余裕を失ってしまうことがあります。
介護で退職を考える前に、打開策を探ってみましょう。本記事では、介護を理由に退職する人の現状と退職する前に検討すべきことを具体的にご紹介します。参考にして、金銭的・精神的に余裕がある介護を目指してください。
介護を理由に退職する人の現状
介護を理由に退職する人の数、年齢層を把握しましょう。あなたが退職を考えているなら、自分以外の人がどのような環境にあるのかを知ると、自分がとるべき行動が明確になることがあります。
介護のために退職する「介護離職」とは?
ご家族の介護のために退職することを「介護離職」と言います。厚生労働省が2017年に調査したデータによると、過去1年間で介護離職をした人は約9.9万人。
この調査によると、介護と就業の両立が難しいと考えている人は、全体の約50%と高い確率で介護離職を意識していることが分かります。一方で、仕事と介護を両立する場合には、「働き方を変えたい」という人が約40%いることから、多くの人が両立できる働き方を模索している事が伺えます。
近年の介護離職者の推移
介護離職者は、2007年で約5万人でしたが、2017年になると約9.9万人と2倍近くに増加しています。過去には女性の離職率が多いことが見て取れますが、近年は男性の離職率も増加傾向です。
経済産業省によると、介護離職による付加価値損失は1年あたり約6,500億円。介護離職は、人材流出・労働力不足につながり企業にとっても深刻な問題で、経済の減速につながるのではと危惧されています。政府は介護離職者を減少させるため、介護の受け皿を拡大すること、仕事と介護の両立が可能な働き方を普及させるなどの取り組みを進めています。
介護離職に踏み切る年代と雇用形態
介護離職に踏み切る年代は、「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」によると、40~50代が多いとされています。およそ6割が既婚であることから、子育て世代が含まれていることも推測されます。また離職者の8割以上が正規雇用職員です。
さらに介護をする人の家族構成を確認してみると、「介護が必要になっても就労している人には兄弟姉妹がいる割合が多い」という興味深いデータが見て取れます。企業にとっても社会にとっても、40~50代の働き盛りが離職することは、大きな痛手です。離職に踏み切る前に、以下にご紹介する方法を試すことをおすすめします。
介護を理由に退職するメリット
介護を理由に退職する「介護離職」のメリットは、以下のことが考えられます。退職を考えているあなたが、「優先したいものは何か」を考えながら確認してください。
介護に集中できる
介護離職をすると、介護に集中できるというメリットがあります。仕事を続けながら介護をすると、要介護者様のスケジュール管理や対応なども並行して行う必要があるため、ときには仕事が疎かになってしまうことも。
介護離職をして「どちらも中途半端」という状態から脱すると、介護に集中できるため住まいが遠方の場合には泊まり込みで介護をしたり、時間をかけて双方のコミュニケーションを深めたりが可能になり、介護者様・要介護者様ともに満足度が高い介護につながります。
介護費用の削減ができる
介護離職により、介護費用の削減が可能です。仕事を続けながら介護をする場合には、訪問介護やデイサービスを利用しながら両立を図るケースがほとんどです。出張や残業が続くときには、ショートステイの利用も検討しなければなりません。その他、身体状況によってはお弁当の配達サービスや見守りサービスが必要なことも。
介護離職をすれば、これらのサービスをすべて抑えることが可能になり、介護中心の生活になります。また日中に動けるようになるため予定を立てやすくなり、結果として延長料金や時間外サービスの削減につながります。
介護を理由に退職するデメリット
介護離職によって発生するデメリットは、以下のものが考えられます。これらのデメリットが受け入れられる状況で、メリットを享受したいと思う気持ちがあるなら介護離職を考えても良いでしょう。
収入が減少する
介護離職に踏み切ると、収入が減少することが考えられます。前述したように、介護離職が多い年齢層は安定した収入が見込める40~50代。養う家族がいるなら、生活を維持するだけの貯蓄・収入を確保しなければなりません。
また「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」によると、介護離職後に再就職を希望した場合、1年以上の期間を要したケースが男性で38.5%、女性で52.2%というデータがあり、「仕事と介護の両立」ができる職場という条件がつくと、再就職が容易ではないということが伺えます。
精神的ダメージを受けることがある
意外にも、介護離職により精神的ダメージを受けるという報告もあります。介護離職により、体力的・時間的に落ち着いて介護ができる環境になると考えられますが、社会との交流が断たれ収入がなくなるため、不安定になるのです。
収入がなくなったために、介護サービスを減らせば、介護者様の体力的・精神的ストレスは大きくなります。常に要介護者様と顔を合わせていなければならないため、イライラして八つ当たりすることも。これらの状況を避けるために、たとえ短時間でもそれぞれに社会との関わりを持つ時間を作ることをおすすめします。
退職の前に利用・検討すべきこと
介護離職にはメリットだけではなく、デメリットも多く存在します。介護離職を決断する前に、職場と相談しながら利用・検討すべきことを把握しましょう。
提案1:職場の介護休業制度を利用する
介護離職をする前に、職場の介護休業制度が利用できないかを相談してみましょう。「介護をしている人の9割が制度を利用していない」というデータがあり、制度を利用せず離職に踏み切っている現状があります。
30人以上の事業所なら、7~10割の事業所が介護休業制度を設けています。利用率が低いため、今後は有給休暇を取得するイメージで制度を利用できる環境が必要です。普段から職場でコミュニケーションを取り、自分の仕事を引き継いでくれる人、介護を理解してくれる人に話して、休業取得のハードルが下がる環境を作りましょう。
提案2:短時間勤務の措置を受ける
「介護休業制度を利用するほどではない」と判断するなら、職場で短時間勤務の措置について相談してみましょう。労働者が要介護状態にある対象家族を介護する場合、以下のいずれかの制度が利用できます。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 時差出勤の制度
- 介護費用の助成制度
要介護者様1人につき、利用開始日~3年以上の期間で2回以上取得することが可能です。3年間まるまる短時間勤務をしても良いですし、途中介護休業を挟んで利用することもできます。
提案3:リモートワークを活用する
介護離職を決断する前に、リモートワークを活用してみましょう。新型コロナウイルスの蔓延をきっかけに、多くの職場でリモートワークが普及しました。環境が整っている職場であれば、業務内容によっては仕事を続けることが可能です。
昼間に要介護者の受診や送迎といったこともできるため、スケジュールをうまく管理すれば両立ができるでしょう。通勤時間も削減できるため、朝・晩の食事介助が必要な場合には効率的です。一度職場に問い合わせてみましょう。
提案4:有料老人ホーム・在宅介護サービス利用を検討する
退職を考えているのなら、有料老人ホーム・在宅介護サービスの利用を検討してはいかがでしょう。サービスを利用すると、一時的に支出は増えますが、将来的に介護の必要がなくなった場合、これまで通りの生活に戻ることができます。
たとえ正規雇用ではなくても、要介護者様が入所中・サービス利用の時間を労働時間に充てられるため収入の確保が可能です。要介護者様は、専門スタッフから入浴介助やレクリエーションを安心して受けることができ、介助者様は介護から離れることができるため息抜きになります。
相談相手を持とう
ご家族に介護が必要な状況になったら、相談相手を持ちましょう。悩みを聞いてくれる人がいれば孤立することがなく、経験者や専門家であれば、的確なアドバイスや対応方法を助言してくれることもあるでしょう。
職場では自らの状況を共有する
ご家族に介護が必要になったとき、まず相談するべき場所は職場です。突発の休暇や早退などが続けば、職場の同僚が不信感を持つからです。状況を自ら事前に説明すれば、理解を得やすくなります。
同僚の手を借りた時には、お礼も忘れずに。そして体力的・時間的に余裕があるときには、積極的に仕事に取り組みましょう。職場であなたの状況が共有されていれば、同僚からも声をかけてもらいやすくなります。
ケアマネージャーに相談する
ご家族に介護が必要になったら、ケアマネージャーに相談するのも良い方法です。あなたの気持ちを率直に話しておきましょう。「仕事を続けたい」という意志があれば、仕事と介護が両立できる施設や介護サービスを紹介してくれることがあります。
要介護者様が定期的に通院しているなら、病院のソーシャルワーカーに相談することも可能です。一人で抱え込まずに、専門家の手を借りながら「自分が求める生活」ができるようアドバイスを受けましょう。
家族・親族に協力要請をする
ご家族に介護が必要になったら、兄弟姉妹・親族に協力を要請しましょう。困難な状況を伝え、助けが必要なことをはっきりと伝えれば、手を貸してくれる人もいるはずです。
「長期休暇時に限ってなら協力できる」「昼間の時間帯なら協力できる」と時期と時間帯がはっきりしたら、あなたも仕事を続けられる可能性があります。兄弟姉妹によっては、介護の協力が得られなくても、資金面での協力や電話での安否確認などできる範囲で何らかの協力をしてくれることがあるでしょう。
地域包括支援センターに相談する
お住まいの地域に設置されている地域包括支援センターも、介護が必要になったご家族の相談を受けてくれます。地域包括支援センターは、看護師や社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門家が常駐するため、介護に関する有意義な情報を提供してくれるでしょう。
地域包括支援センターは、一般的に市区町村に1か所以上設置されており、無料で相談を受けてくれます。地域によっては名称が異なることがあるため、市区町村のホームページや電話で確認しておくことをおすすめします。
退職に踏み切る前に制度を利用してみよう
家族に介護が必要になったとき、体力的・時間的余裕を優先してすぐに退職することはおすすめできません。現在は制度が整っているにもかかわらず、利用せずに介護離職に至る例が多い状況です。まずは周囲に状況を話して、理解してもらいましょう。
介護はいつまで続くか分からないもの。だからこそ、「続けられる生活」を意識する必要があります。すべてを完璧にこなそうと思わず、肩の力を抜いて共倒れしない環境を目指しましょう。