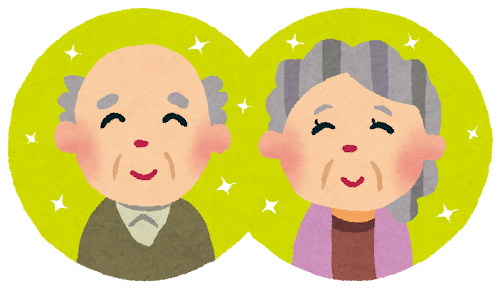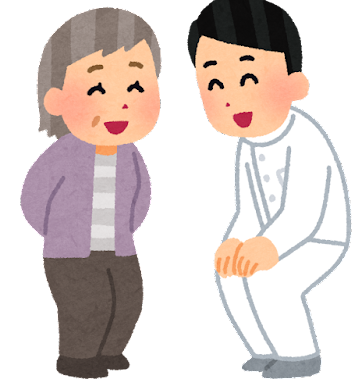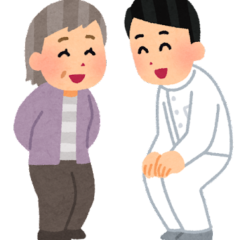小規模多機能型居宅介護なら費用が定額!内訳と費用を抑える工夫を紹介
小規模多機能型居宅介護は、1度の契約で3つのサービスを利用することができます。契約の手間が省けるだけではなく、利用者様のニーズに沿った利用ができるため評判です。
しかし実際に利用するにあたって、正しく理解しておきたいのは費用の仕組み。他のサービスとは利用の回数や時間が異なるため、自分に適した利用ができるかをもう一度確認しましょう。
この記事では、小規模多機能型居宅介護にかかる費用の内訳やメリット、費用を抑えるための制度・工夫をご紹介します。参考にして、小規模多機能型居宅介護を検討してみてはいかがでしょうか。
小規模多機能型居宅介護の費用内訳
小規模多機能型居宅介護の費用は、おもに以下の3つから成り立っています。事前に費用内訳を知っておくと、利用する施設に質問したり利用者様の状況を伝えたりできるため、より細かい料金を知ることができますよ。
1:定額料金
以下、厚生労働省より小規模多機能型居宅介護の定額料金をご紹介します。小規模多機能型居宅介護の利用料は、月額定額制です。
| 要介護度 | 利用者様が同一建物に居住していない場合 | 利用者様が同一建物に居住する場合 |
| 要支援1 | 3,403円 | 3,066円 |
| 要支援2 | 6,877円 | 6,196円 |
| 要介護度 | 利用者様が同一建物に居住していない場合 | 利用者様が同一建物に居住する場合 |
| 要介護1 | 10,320円 | 9,298円 |
| 要介護2 | 15,167円 | 13,665円 |
| 要介護3 | 22,062円 | 19,878円 |
| 要介護4 | 24,350円 | 21,939円 |
| 要介護5 | 26,849円 | 24,191円 |
いずれも利用者負担が1割の場合、1ヶ月ごとの料金です。実際の金額は、「定額+以下に示す加算料金」を合算した金額になります。
2:施設により異なる加算料金
上記した定額料金に加えて、施設によって加算される料金があります。施設の規模やスタッフの状況によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
具体的には、スタッフの配置や訪問回数によってかかる訪問体制強化加算や、スタッフの勤続年数・介護福祉士の割合によってかかるサービス提供体制強化加算があります。その他、看護職員配置加算や看取り連携体制加算など、施設の運営体制に応じた加算がされます。
1つ当たりの加算は少額ですが、複数加算がかかると負担になることも考えられため、疑問点は施設に問い合わせてみましょう。
3:利用者様にかかる食費・おむつ代など
小規模多機能型居宅介護を利用するには、定額料金・施設ごとにかかる加算料金のほか、食費やおむつ代などが必要です。宿泊を伴う場合には、別途宿泊費もかかります。これらは介護保険適用外のため、全額自己負担です。
食費は1食300~800円程度で提供されることが多く、おむつや歯ブラシなどを施設側から提供してもらった場合には、数百円かかります。宿泊費は、施設の立地や部屋のタイプによって異なりますが、1泊2000~5000円程度です。
小規模多機能型居宅介護の基本料金は毎月定額ですが、これらの自己負担費用は、サービスの利用頻度によって変動します。利用が多い月と少ない月では、費用が異なることを覚えておきましょう。
利用が多い人は小規模多機能型居宅介護がお得
日頃からサービスの利用が多い人は、小規模多機能型居宅介護がお得です。利用が多い人は、なぜ小規模多機能型居宅介護がお得なのかをご説明します。
介護保険支給限度基準額からはみ出す心配がない
小規模多機能型居宅介護は、介護保険支給限度基準額からはみ出す心配がありません。小規模多機能型居宅介護は、毎月基本料金が同額だからです。
介護保険支給限度基準額は、要介護状態によって決められており、基準額範囲内でサービスを利用する場合には、所得に応じて1~3割の費用がかかります。仮に基準額範囲を超えてサービスの利用をした場合、超えた分は全額自己負担になってしまうのです。
よってデイサービスやショートステイなどそれぞれ契約・利用をすると、状況によっては介護保険支給限度基準額を超えてしまうことがあります。週の半分以上サービスを利用する場合には、小規模多機能型居宅介護がお得といえるでしょう。
利用回数に制限がない
小規模多機能型居宅介護は、利用回数に制限がありません。一般的には通所型サービス、訪問型サービスともに、要介護度によって利用回数が決まっています。要介護度が高くになると利用回数が増えますが、身体に変化がなく利用回数を増やしたい場合には、自己負担で対応するほかありません。
その点、小規模多機能型居宅介護は各サービスの利用定員数さえクリアしていれば、何度でも利用が可能です。
さらに小規模多機能型居宅介護の契約を済ませれば、通い・訪問・宿泊の3つのサービスを利用することができるため、利用者様の生活状況に応じて柔軟なサービスを提供してくれます。
併用可能なサービスを利用してマストなサービスをカバー
小規模多機能型居宅介護は、それぞれ条件が伴いますが以下のサービスなら併用が可能です。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与
- 住宅改修
小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・宿泊サービスを提供することから、同じような以下のサービスは併用できません。
- 居宅介護支援
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- デイケア
- デイサービス
- ショートステイ
小規模多機能型居宅介護は、リハビリを重点的に行う場面が少ないため、小規模多機能型居宅介護の利用時間外に、訪問リハビリを併用することで身体機能の維持・改善が図れます。しかし介護保険支給限度基準額の都合上、訪問リハビリテーションを希望回数利用できないこともあるため、ケアマネージャーと相談しましょう。
費用を抑えるために利用できる制度・工夫
申請や条件が伴うことがありますが、費用を抑えるために利用できる制度や工夫をご紹介します。今後小規模多機能型居宅介護を利用するうえで、参考にしてください。
高額介護サービス費制度を利用する
1ヶ月に支払った利用者負担合計額が負担限度額を超えた時、高額介護サービス費制度が利用できます。収入に応じて、以下のような上限額が設けられています。
| 対象となる人 | 月額の負担上限額 |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,000(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税(前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等) | 24,600円(世帯) |
| 15,000円(個人) | |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
世帯とは住民基本台帳上の世帯員を指し、介護サービスを利用した方全員の合計額になります。個人は、介護サービスを利用した本人のみの負担合計額です。所得が低いほど、月額の自己負担上限額も低くなります。高額介護サービス費制度は、市区町村に申請が必要です。
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度を利用する
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度は、市町村民税世帯非課税であって要件を満たす方のうち、市区町村が生計が困難だと認めた方や生活保護受給者に適用されます。
この制度を利用すれば、軽減制度を実施している介護サービス施設からサービスを提供してもらう際、利用者自己負担額が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減され、3/4にすることが可能です。サービス利用費のほか、食費や居住費、宿泊費にも1/4の軽減が適用されます。
自治体によって対象とするサービスを限定していたり、施設が軽減事業を実施していなかったりすることがあるため、事前に確認しましょう。
利用者様の意思で世帯分離を検討する人も
費用を抑えるために、利用者様の意思のもと世帯分離を検討する人もいます。同じ世帯で親子が生活している場合に、住所はそのままで2つ以上の世帯に分けるのです。
要介護状態の親が世帯から外れると、「低所得者世帯」とみなされるため、負担額を減らすことができます。しかし国民健康保険の支払い額が高くなったり、行政手続きを行う際に手間がかかったりするため、慎重に検討しましょう。
なお世帯分離によって不都合が生じた場合には、再び「世帯合併」することも可能です。世帯分離・世帯合併ともに窓口は市区町村になります。
費用が定額の小規模多機能型居宅介護なら安心して利用できる
小規模多機能型居宅介護は、月額定額制のため介護保険利用限度額からはみ出す心配がありません。サービスをそれぞれ利用するよりも分かりやすく、利用者様のニーズに応じたサービスを提供してくれます。
費用を抑えるためには、制度を利用すると同時に、施設で提供してくれるオムツや歯ブラシなどを持参するのも工夫の一つです。事前に確認して、利用者様とご家族に負担にならない方法をとりましょう。