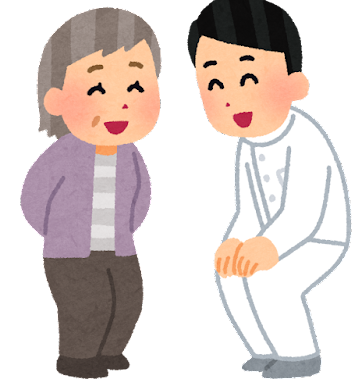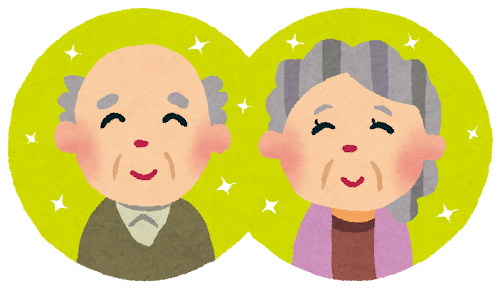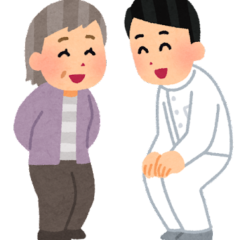小規模多機能型居宅介護のデメリットを見極めて向き不向きを判断する方法
小規模多機能型居宅介護は、1つの介護事業所と契約すれば通所・訪問・宿泊のサービスが利用できるため、便利なサービスです。しかし実際にサービスを利用するなら知っておいて欲しいのがデメリット。
デメリットを知ることで、小規模多機能型居宅介護の基本的知識のほか、ほかのサービスとの違いを深く理解できるようになりますよ。ここでは、小規模多機能型居宅介護の基本的知識のほか、デメリットについてフォーカスし、利用する方の向き、不向きについて考えます。
小規模多機能型居宅介護の特徴
小規模多機能型居宅介護には以下のような特徴があります。利用する方のライフスタイルによって、メリットにもデメリットにもなるため、しっかりチェックしていきましょう。
1つの事業所で3つのサービスを利用できる
小規模多機能型居宅介護は、1つの事業所と契約すれば通所・訪問・宿泊の3つのサービスを利用することができます。すべて1か所で完結するため、わずらわしさがありません。
自宅を拠点としてデイサービスや介護支援、ショートステイなどを利用できるため、利用する方のニーズに合わせて適したサービスを受けることができます。
地域密着型サービスのひとつ
小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスのひとつです。地域密着型サービスは、事業所の所在地と同じ住民票を持つ方を対象としたもので、介護サービスの開始にともなって引っ越しの必要性がありません。
住み慣れた地域でサービスを受けることができるため、利用する方にとって環境が変わらないというのが大きなメリットです。
24時間対応が可能
小規模多機能型居宅介護は、24時間対応が可能です。通所や訪問サービスは、基本的に日中にサービスを提供することが前提になっています。
しかし小規模多機能型居宅介護は宿泊のサービスも提供しているため、家族が自宅を開けなければならないケースでも、安心して預けることができます。
支払いが定額制
小規模多機能型居宅介護は支払いが定額制です。3つのサービスを組み合わせて利用しても同額で、介護保険の利用限度額を超える心配がありません。
利用する方の要介護度や収入によって実際の費用は異なりますが、支払いが毎月大きく変わらない点は、家族にとって安心材料になります。しかし以下の点も、頭に入れておいてください。
加算料金が必要になることがある
小規模多機能型居宅介護は、加算料金が必要になることがあります。施設の体制によって異なり、以下のようなものがあります。
- 初期加算:サービス登録日から30日間、1日あたり30円の加算が生じる。
- サービス提供体制強化加算:スタッフに介護福祉士と常勤職員を増やした場合に生じる加算。
- 認知症加算:認知症の方を受け入れるときに加算される。
これらの加算を考えて、基本料金+α数万円を想定しておくと良いでしょう。
小規模多機能型居宅介護にはデメリットもある
小規模多機能型居宅介護のメリットは分かっていただけたと思います。しかし実際に事業所と契約するときに知っておいて欲しいのはデメリットです。契約後に後悔しないために、以下の点を確認しましょう。
デメリット1:定員数が少ない
小規模多機能型居宅介護のデメリットとして、定員数が少ない事が挙げられます。3つのサービスに利用回数制限はありませんが、それぞれ定員数が決められているのです。1日あたりの各定員数は以下のとおりです。
- 通所:15名以下
- 宿泊:9名以下
- 事業所の登録定員数:29名以下
小規模だからこそきめ細かいサービスを受けられますが、希望するサービスが定員数を超えていた場合には、柔軟に利用できないことがあります。
デメリット2:サービス利用が少ないと割高になる
小規模多機能型居宅介護のデメリットとして、サービス利用が少ないと割高になることがあります。小規模多機能型居宅介護は毎月の支払いが定額制とお伝えしましたが、月によって利用回数が少ない場合でも、基本料金は同額だからです。
目安として要介護1の方が自己負担額1,000円のデイサービスを利用した場合を比較すると、月10回の利用なら10,000円ですが、小規模多機能型居宅介護を利用した場合の月額負担額は10,320円になり、デイサービスだけの契約のほうが安く済みます。契約前に、具体的にどのようなサービスを月何回利用したいかを予測してみましょう。
デメリット3:併用できないサービスがある
小規模多機能型居宅介護では、併用できないサービスがあります。それぞれのサービスを契約する場合には決まりはありませんが、小規模多機能型居宅介護を提供する事業所と契約する際には、これまで利用できたサービスが利用できなくなる可能性があります。
| 居宅介護支援 | 訪問介護 | 訪問入浴介護 |
| デイケア | デイサービス | ショートステイ |
小規模多機能型居宅介護でカバーできることが多いですが、上記のサービスは併用不可とされているため注意が必要です。
それぞれのサービスと小規模多機能型居宅介護の違い
小規模多機能型居宅介護の特徴、デメリットを理解して頂いたところで、それぞれのサービスと小規模多機能型居宅介護を比較してみましょう。利用する方に適したサービスかどうかを考えながら確認してみてください。
デイサービスと小規模多機能型居宅介護の違い
小規模多機能型居宅介護の「通所」は、デイサービスと違い「スポット利用」が可能です。午前中だけ、夕方だけという利用ができるため、利用する方のニーズに沿ったサービスが提供されます。
一方でデイサービスはあらかじめ決まった時間枠で利用することになりますが、小規模多機能型居宅介護よりもレクリエーションやイベントが多い傾向です。同じ「通所」のサービスでも、利用する方が「何を求めるのか」で判断することをおすすめします。
訪問介護と小規模多機能型居宅介護の違い
小規模多機能型居宅介護の「訪問」は、訪問介護と比較して「必要なサービスをオーダーメードで利用できる」ことが特徴です。安否確認や傾聴だけという場合でも、利用することができます。
さらに小規模多機能型居宅介護の「訪問」は、費用や時間枠にとらわれることがありません。しかしサービスそのものに不満がある場合には、訪問介護のように「事業所を変更すれば解決する」というわけではないため、注意が必要です。
ショートステイと小規模多機能型居宅介護の違い
小規模多機能型居宅介護の「宿泊」は、定員数を満たしていなければ急な宿泊でも対応が可能です。一方でショートステイの場合には事前予約制を取ることが一般的で、あらかじめ家族も予定を合わせなければなりません。
しかし小規模多機能型居宅介護の「宿泊」の場合には、「通所」からそのまま「宿泊」することができるため、万が一家族に急な用事が生じた場合でも1ヶ月の定額範囲内で対応してくれます。
小規模多機能型居宅介護が向いている人
小規模多機能型居宅介護の利用は、以下の方が向いているといえます。
- 同居する家族が忙しい方
- 毎回顔見知りのスタッフからサービスを受けたい方
- 費用面に不安を抱く方
小規模多機能型居宅介護は、在宅で暮らす方を対象としています。よって住み慣れた家で生活しながら、家族や利用する方の都合でサービスを受けることが可能です。小規模多機能型居宅介護は、1つの事業所と契約をすれば通所・訪問・宿泊のサービスを受けられるため、通所で関わったスタッフが宿泊で対応してくれることも。費用は定額制なので、安心してサービスを受けられます。
小規模多機能型居宅介護が向いていない人
小規模多機能型居宅介護は、以下の方は残念ながら向いていないと考えられます。
- 現在利用している通所サービスや訪問介護で、良好な人間関係が築けている方
- サービスや施設ごとにできるだけ多くの人と関わりたい方
- 介護サービスの利用回数が少なく、利用分だけを支払いたい方
小規模多機能型居宅介護を利用するにあたっては、これまでのケアマネージャーから小規模多機能型居宅介護を提供する事業所のケアマネージャーに変更しなければなりません。現状に満足している場合には、利用する方の意見に耳を傾けて慎重に行動しましょう。なお、小規模多機能型居宅介護は利用回数によらず月々の支払い額は同じです。
小規模多機能型居宅介護を利用するには
小規模多機能型居宅介護を利用するには、以下の手順で進めるとスムーズです。
ステップ1:利用条件を確認する
小規模多機能型居宅介護の利用を検討する前に、利用条件を満たしているかを確認しましょう。利用条件は以下のようになっています。
- 要支援1以上もしくは要介護1以上の認定を受けている。
- 契約を検討している事業所と同じ自治体に住民票を置いている。
小規模多機能型居宅介護は要介護認定を受けている方が対象です。小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスのため、事業所と同じ自治体に住民票を置いている方しか利用できません。
ステップ2:施設の見学をする
利用条件を確認したら、地域包括支援センターや担当のケアマネージャーに相談しながら、事業所を選定することをおすすめします。空き状況や雰囲気を教えてもらえるからです。
その後可能であれば、利用する方自身が施設見学をしましょう。事前に「どのようなサービスを望んでいるか」を明確にしておくと、より適したサービスを探すことができます。
ステップ3:利用事業所と契約する
事業所の見学をして利用する方の了承が得られれば、いよいよ事業所との契約です。契約前に事業所との面談が行われ、利用する方の身体状況や必要なサービスなどを確認します。
小規模多機能型居宅介護を提供する事業所と契約すると、ケアマネージャーを変更しなければならないことを覚えておきましょう。
ステップ4:ケアプランの作成・実施
無事に事業所との契約が済んだあと、事業所専属のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
ケアプランを作成後、小規模多機能型居宅介護でのサービスが利用開始になるため、この段階で利用する方はもちろん、家族の要望も伝えておくようにしましょう。
デメリットを見極めてニーズを満たしたサービスを受けよう
小規模多機能型居宅介護は、定員数が少ない、サービス利用が少ないと割高になる、併用できないサービスがあるなどのデメリットがあります。しかし住み慣れた環境でサービスを受けられるため、利用する方やご家族にとってのメリットが大きい事も事実です。
どのようなサービスをどれくらいの頻度で利用するのかを、専門家に相談してみましょう。きっとご家族にぴったりのサービスを提案してくれますよ。