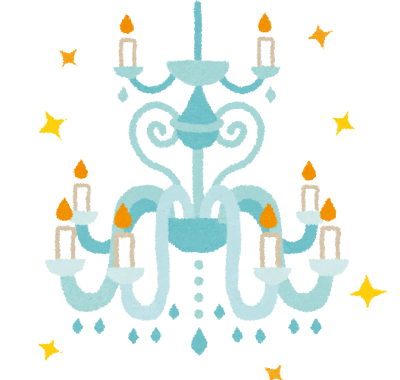訪問介護とは?サービス内容・料金・できること・手続きまでやさしく解説
「訪問介護って、どんなことをしてくれるの?」そんな疑問をお持ちの方へ。
訪問介護は、介護職員がご自宅を訪れ、入浴・排泄・掃除などの日常を支える制度です。
住み慣れた家で、できるだけ自立した暮らしを続けたい…そんな思いに寄り添います。
とはいえ、「誰が使えるの?」「費用は?」など、初めてだと分かりづらいことも多いはずです。
そこで本記事では、訪問介護の内容・手続き・費用の目安などを、わかりやすくご紹介します。
以下のような点が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
|
迷いながらも大切な選択をしようとしているあなたへ。
この記事が、最初の一歩を後押しし、安心して介護サービスを検討できるきっかけになれば幸いです。
訪問介護とは?制度の概要と基本ポイント

訪問介護は、介護を必要とする方が自宅で生活を続けられるよう支援する制度です。
介護保険のサービスのひとつとして位置づけられており、要介護認定を受けた方を対象に、専門職が定期的に自宅を訪問して生活を支えます。
そこで、訪問介護の基本ポイントは次の通りです。
|
制度を正しく理解しておくことは、後悔のない介護サービス選びの第一歩となります。
とくに初めて介護と向き合うご家族にとって、訪問介護は現実的かつ安心して使える選択肢といえるでしょう。
訪問介護の定義と目的
訪問介護とは、要介護認定を受けた方の自宅に、介護職員が定期的に訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスです。
厚生労働省が定めた制度に基づき、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類の支援が用意されています。
こうした支援の目的は、利用者が可能な限り自立した暮らしを維持できるよう支えることにあるのです。
入浴や排泄といった身体的な介助から、掃除や調理などの家事支援まで、内容は幅広く、ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って柔軟に組み合わされます。
なぜ「在宅介護」が重要視されているのか
日本では高齢化が急速に進み、現在では65歳以上の人口が全体の約3割を占めています。
こうした背景の中で、すべての高齢者が施設で暮らすのは現実的ではなく、自宅での生活を支える「在宅介護」の重要性が増しています。
特に、認知症の初期段階や身体機能が部分的に残っている方にとっては、生活環境を変えずに支援を受けられることが心身の安定につながるのです。
また、家族と共に過ごしながら介護を受けられるという点も、訪問介護が広く選ばれている理由のひとつといえるでしょう。
ホームヘルパーと訪問介護の違い
「ホームヘルパー」と「訪問介護」は混同されやすい言葉ですが、制度的な意味合いや契約形態、費用の負担において明確な違いがあります。
正しく理解しておかないと、介護保険が使えない自費契約となってしまう可能性もあるため、あらかじめ両者の違いを確認しておくことが重要です。
※以下は一般的な違いであり、自治体や事業所によって若干異なる場合があります。
ホームヘルパーと訪問介護の主な違い
| 違いのポイント | 訪問介護
(介護保険サービス) |
ホームヘルパー
(一般的な呼称) |
| 提供主体 | 介護保険指定事業所(介護保険制度に基づく) | 民間企業、個人、NPOなど(保険適用外が多い) |
| 利用契約 | ケアプランに基づく契約 | 利用者との直接契約(自由契約) |
| 利用料金 | 介護保険が適用される(自己負担1〜3割) | 全額自己負担となるケースが多い |
| サービス内容 | 身体介護、生活援助、通院等乗降介助 | 生活支援が中心。医療的ケアは原則不可 |
| 資格・研修 | 初任者研修・実務者研修など所定の資格が必要 | 資格不問のケースもあり、事業者により異なる |
上記のように、「訪問介護」は介護保険制度の中で提供される公的サービスであり、費用の面でも利用者にとってメリットがあります。
一方、「ホームヘルパー」はより柔軟な支援が可能な反面、制度的な裏付けや費用負担の点で注意が必要です。
目的や希望する支援内容に応じて、どちらを選ぶべきかを判断しましょう。
訪問介護の3つのサービス内容

訪問介護では、利用者の体調や生活環境に合わせて、3つの支援が提供されます。
主な内容は、身体に直接触れて介助を行う「身体介護」、日常の家事を助ける「生活援助」、そして外出時の付き添いを含む「通院等乗降介助」です。
これらのサービスは、ケアマネジャーが作成するケアプランをもとに、必要な頻度や内容で組み合わせて実施されます。
どんな支援が受けられるのかを事前に理解しておくことが、訪問介護を効果的に活用する第一歩といえるでしょう。
身体介護(入浴・排泄・食事など)
身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う日常動作の支援です。
排泄や入浴、食事、移動、服薬など、生活の質を大きく左右する支援が含まれます。
【身体介護の主なサービス内容(例)】
| 支援内容 | 具体例 |
| 入浴介助 | 浴室への誘導、洗身・洗髪、着脱介助など |
| 排泄介助 | トイレ誘導、おむつ交換、ポータブルトイレの設置等 |
| 食事介助 | 配膳・食事のサポート、服薬の見守り |
| 移動・体位交換 | ベッドからの起き上がり、車椅子移乗、寝返り補助 |
| 清拭・口腔ケア | タオルでの全身清拭、歯みがきやうがいの支援 |
身体状況により必要な支援は異なり、ケアマネジャーによるアセスメントに基づいて、適切な内容と時間が決定されます。
利用者が尊厳を保ちながら過ごせるよう、きめ細かな対応が求めらるのです。
生活援助(家事支援)
生活援助は、身体介助に該当しない家事全般の支援です。
利用者が自宅で快適に暮らすために欠かせない支援ですが、同居家族の有無などで提供範囲が変わるため注意が必要です。
生活援助の主な支援内容(例)
| 支援内容 | 具体例 |
| 掃除 | 居室・トイレ・キッチンなどの清掃 |
| 洗濯 | 洗濯機の操作、干す・たたむ・収納など |
| 調理 | 一般的な家庭料理の作成、配膳、片づけ等 |
| 買い物 | 日用品や食材の購入代行(必要な場合) |
| 整理整頓 | 室内の片づけ、ゴミ出し、布団の上げ下ろしなど |
ただし、本人以外のための家事(家族の食事や洗濯など)や、日常の範囲を超える作業(家具の移動・草むしりなど)は対象外です。
介護保険制度では「本人の生活支援」に限定されており、ケアマネジャーの判断に基づき提供されます。
通院等乗降介助(外出サポート)
通院等乗降介助は、利用者の通院や外出を安全にサポートする支援です。
具体的には、玄関から車までの移動や、車への乗り降り、そして病院の受付までの付き添いなどが含まれます。
ただし、単なる送迎や外出の同行は対象外とされています。
あくまで「医療目的の移動」として認められたケースに限定されるため、事前にケアマネジャーとしっかり相談することが大切です。
訪問介護でできないこと一覧とその理由
訪問介護では、すべての要望に応えられるわけではありません。
たとえば医療行為や、利用者以外の家族への家事代行、日常生活に直接関係しない修理や草むしりなどは、制度上の対象外です。
これらの行為は「介護保険の目的から逸脱する」とされており、誤って依頼するとトラブルにつながることもあります。
サービスの限界を知ることが、賢い使い方につながるのです。
誰が使える?訪問介護の対象者と利用条件
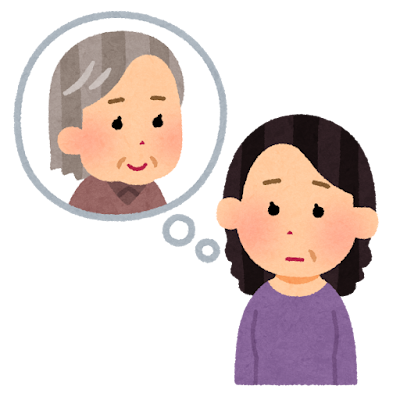
「訪問介護を使いたい」と思っても、すぐに使えるとは限りません。
基本的には、要介護認定を受けている方が対象です。
また、同じ在宅介護でも「要支援」の方は、別の制度を利用する仕組みとなっています。
制度の枠組みを正しく理解し、自身の状況にあわせた手続きを行うことが、スムーズなサービス利用の第一歩となります。
訪問介護の対象となる人の条件
訪問介護を利用できるのは、介護保険で「要介護1~5」と認定された方です。
一方で、「要支援1・2」と判定された場合は、「介護予防訪問介護」あるいは「総合事業」の対象となります。
どちらも自立支援を目的としていますが、内容や申請の流れが異なるため、事前に制度の違いを確認しておく必要があります。
要介護認定の流れと必要書類
訪問介護を受けるには、まず市町村に要介護認定の申請を行います。
提出後は、本人への聞き取り調査や医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護度が判定される流れです。
申請から結果が出るまでには、通常1か月ほどかかります。
余裕を持った準備と、必要書類の早めの提出がポイントといえるでしょう。
ケアマネジャーが必要な理由
訪問介護を利用する際には、ケアマネジャーによるケアプランの作成が欠かせません。
このプランには、どのような支援をどの頻度で受けるかといった内容が細かく盛り込まれています。
ケアマネジャーとの関係がうまく築けていると、訪問介護の質や満足度にも大きく影響します。
信頼できる専門職と連携することで、介護生活の不安を軽減できるはずです。
訪問介護の利用開始までの流れと準備
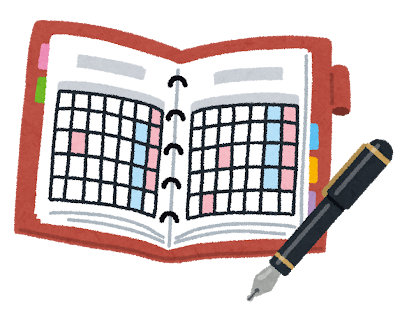
訪問介護を利用するには、事前の相談から契約に至るまで、いくつかの手順を踏む必要があります。
とくに初めて介護に関わる方にとっては、不安や戸惑いを感じやすい場面も多いもの。
どこに相談すればいいのか、どのように事業所を選ぶのか…この流れをしっかりと把握しておくことで、スムーズなサービス開始につながります。
地域包括支援センターへの相談からスタート
「もしかして介護が必要かも…」そう感じたとき、まず最初に相談すべき窓口が地域包括支援センターです。
市区町村ごとに設置されており、介護・福祉・医療に関する公的な無料相談が可能です。
ここでは、専門の職員(保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなど)が常駐しており、状況を丁寧にヒアリングしたうえで、適切な支援策や申請手続きの案内をしてくれます。
介護保険の申請やサービス内容について迷ったら、まずこのセンターに連絡するのが第一歩といえるでしょう。
ケアプランの作成とサービス事業所の選定
要介護認定を受けたあとは、ケアマネジャーとともに「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。
このプランをもとに、どの訪問介護事業所を利用するかを決めていきます。
事業所を選ぶ際は、以下のような視点が重要です。
|
また、事前に見学や面談が可能な事業所もありますので、実際に足を運んで印象を確かめるのもおすすめです。
契約から初回訪問までのステップ
訪問介護事業所が決まったら、いよいよ契約の手続きに進みます。
契約前には、以下のような事項をしっかり確認しておきましょう。
|
その後、「初回の訪問日を調整し、介護職員との顔合わせ(初回面談)」を行います。
| ここでは生活状況や希望を直接伝えることができ、以後の支援にも大きく影響する重要な時間です。
訪問介護の利用は、単なる「契約」ではなく、生活の一部を支えるパートナーを迎えることでもあります。 信頼関係の第一歩を、大切に築いていきましょう。 |
訪問介護の保険適用と自己負担の目安

訪問介護の費用は、サービスを利用する際にもっとも気になるポイントのひとつです。
「介護保険が適用されるとはいえ、実際にはいくらかかるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、1回あたりの基本料金から月額の目安及び自費サービス等、具体的にご紹介します。
1回あたりの基本料金と区分別料金
介護保険を使った訪問介護の料金は、「サービスの種類」と「所要時間」によって決まります。
また、地域区分や加算要件によって若干変動する場合もあります。
以下は、自己負担1割の場合のおおよその目安です。
※あくまで参考金額であり、実際の負担額は地域や事業所によって異なる場合があります。
身体介護の目安(1回限り)
| サービス時間 | 自己負担額(1割) |
| 20分未満 | 約170円 |
| 20~30分 | 約250円 |
| 30~60分 | 約400円 |
| 60~90分 | 約580円 |
生活援助の目安(1回限り)
| サービス時間 | 自己負担額(1割) |
| 20~45分 | 約200円 |
| 45分以上 | 約250円 |
このように、身体介護のほうが生活援助よりも高めに設定されています。
理由は、直接的な身体的サポートが求められるためといえるでしょう。
月額料金のシミュレーションと負担軽減制度
訪問介護の利用頻度によって、月あたりの支払い額も変わってきます。
以下は要介護2の方が身体介護30分程度の支援を受けた場合の月額目安です。(1割負担の場合)
月額料金の例
| 利用頻度 | 月の目安回数 | 自己負担額 |
| 週1回 | 約4回 | 約1,600円 |
| 週3回 | 約12回 | 約4,800円 |
| 週5回(毎日) | 約20回 | 約8,000円 |
(※上記金額に加算や交通費が含まれる場合は、もう少し高くなる可能性もあります。)
さらに、一定以上の負担額になった場合には「高額介護サービス費」が適用され、月額の上限が設定されます。
収入に応じて自己負担限度額が異なり、住民税非課税世帯では月額15,000円に抑えられるケースもあります。
こうした制度を知っておくことで、安心してサービスを継続しやすくなります。
自費サービスの費用相場と注意点
介護保険の対象外となる支援を希望する場合、全額自己負担の「自費サービス」を利用することになります。
たとえば以下のような内容です。
|
こうしたサービスは事業所ごとに価格が異なりますが、1時間あたり2,000〜4,000円程度が相場とされています。
中には30分単位で設定されているところもあります。
注意点として、介護保険と自費サービスは契約形態が異なるため、利用前に「どこまでが保険内か」「追加料金の有無」などを明確にしておくことが大切です。
訪問介護事業所の選び方と6つの視点
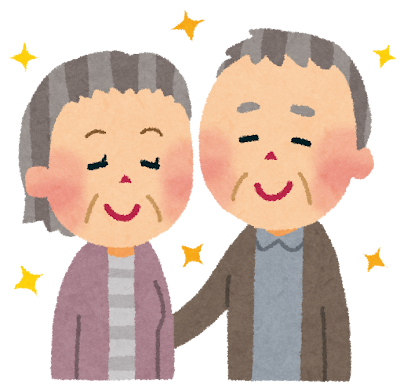
訪問介護は、利用者との信頼関係が何より重要です。
だからこそ、「どの事業所を選ぶか」で介護の質も満足度も大きく変わってきます。
ここでは、後悔しないために確認しておきたい6つの視点と、実際にあったトラブル例をご紹介します。
良い事業所を選ぶための6つの視点
以下の6つのポイントは、訪問介護の事業所選びで特に注目したい要素です。
|
これらを踏まえて比較・見学することで、納得のいく選択がしやすくなります。
実際にあったトラブル例と回避策
訪問介護では、思わぬトラブルが起こることもあります。
以下に代表的な事例を挙げ、その対策も確認しましょう。
|
トラブルを未然に防ぐには、事前の確認と、信頼できる窓口の存在が何より大切です。
訪問介護に向く人の適性と他サービスの比較
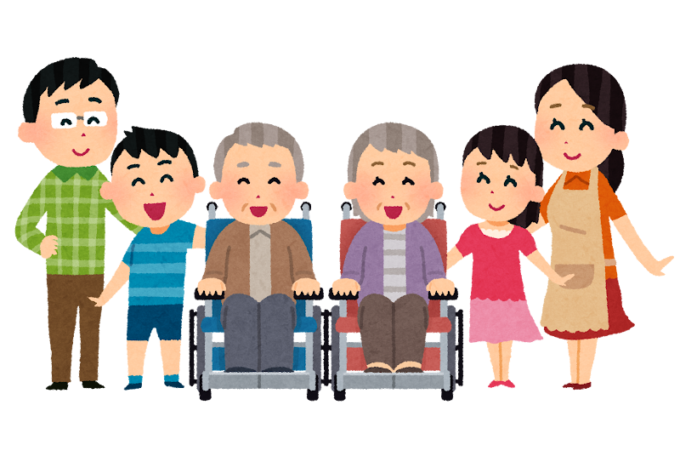
訪問介護は、在宅で暮らし続けたい方にとって心強い選択肢ですが、すべての人にとって最適とは限りません。
支援を受けながらも日常生活をある程度こなせる方に向いている一方で、重度の支援が必要な方には他のサービスが適している場合もあります。
ここでは、訪問介護の「向き・不向き」と、それに応じた代替サービスをわかりやすく解説します。
訪問介護が適している人の特徴
訪問介護がぴったり合うのは、在宅生活を基本としながら、部分的な支援を必要とする方です。
たとえば、次のようなケースが挙げられます。
|
このような方であれば、訪問介護によって暮らしの一部を支えながら自立を保つことができるとされています。
特に、住み慣れた家で安心して過ごしたいという気持ちを大切にしたい方にとって、大きな安心感につながるでしょう。
訪問介護が合わないケースと代替サービス
一方で、訪問介護では対応が難しいケースもあります。
たとえば次のような状況では、他の介護サービスとの併用や切り替えを検討する必要があります。
|
このような場合には、次のような代替サービスが検討されます。
| 状況 | 適するサービス | 内容の概要 |
| 日中の長時間ケアが必要 | 通所介護(デイサービス) | 食事・入浴・機能訓練を含む日帰り支援 |
| 家族不在で在宅生活が困難 | 小規模多機能型居宅介護 | 通い・泊まり・訪問が一体化した支援 |
| 認知症の進行により安全確保が困難 | 認知症対応型通所介護/グループホーム | 認知症に特化した介護体制 |
| 一時的な宿泊が必要 | ショートステイ | 施設に短期間宿泊し、食事・介護を受ける |
こうした選択肢は、訪問介護と排他的ではなく、併用しながら柔軟に組み合わせることも可能です。
利用者本人と家族の状況、そしてケアマネジャーの判断をもとに最適なケア体制を整えていくことが大切となります。
訪問介護のまとめ
訪問介護は、自宅で安心して暮らし続けるための心強い制度です。
身体介護や生活援助、通院時の介助など、生活に密着した支援が受けられます。
ただし、利用には要介護認定が必要で、費用や対象範囲にはルールがあります。
ケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携を通じて、必要な支援を無理なく受けることが大切です。
家族や本人の希望に合った形で、暮らしを支える一歩として、ぜひ上手に活用してくださいね。